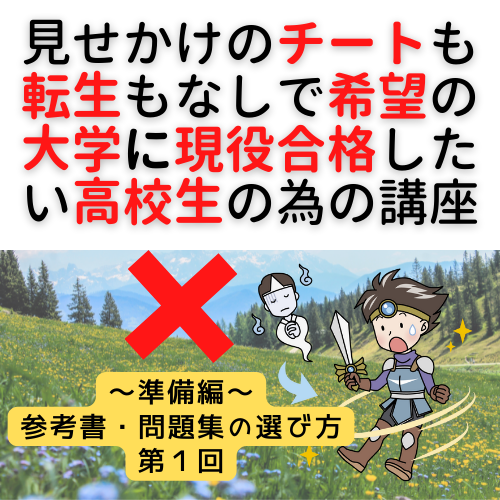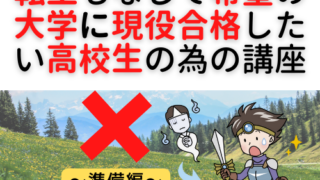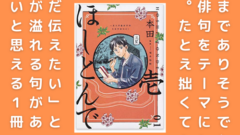参考書・問題集の選び方 第1回
本年度の総合型選抜(旧推薦・AO)試験も山を越えたところです。
1月からの本試験が本命の場合はもう間に合わないかもしれませんが、これから大学受験の勉強を始める人たちにとって、最初の準備が肝心です。
いざ勉強を始めようとした時、
という問いが、とりあえず皆さんの頭の中に浮かんだんじゃないでしょうか?
もしかしたら浮かんでないかもしれないけど、そういうことにして話を進めます。
例えばダンジョンに向かう前には、事前に周到な準備が必要ですよね。
武器や防具はもちろん、水・食料、テントやナイフなどのサバイバル用品、
目的地に達するまでの地図なども必要です。

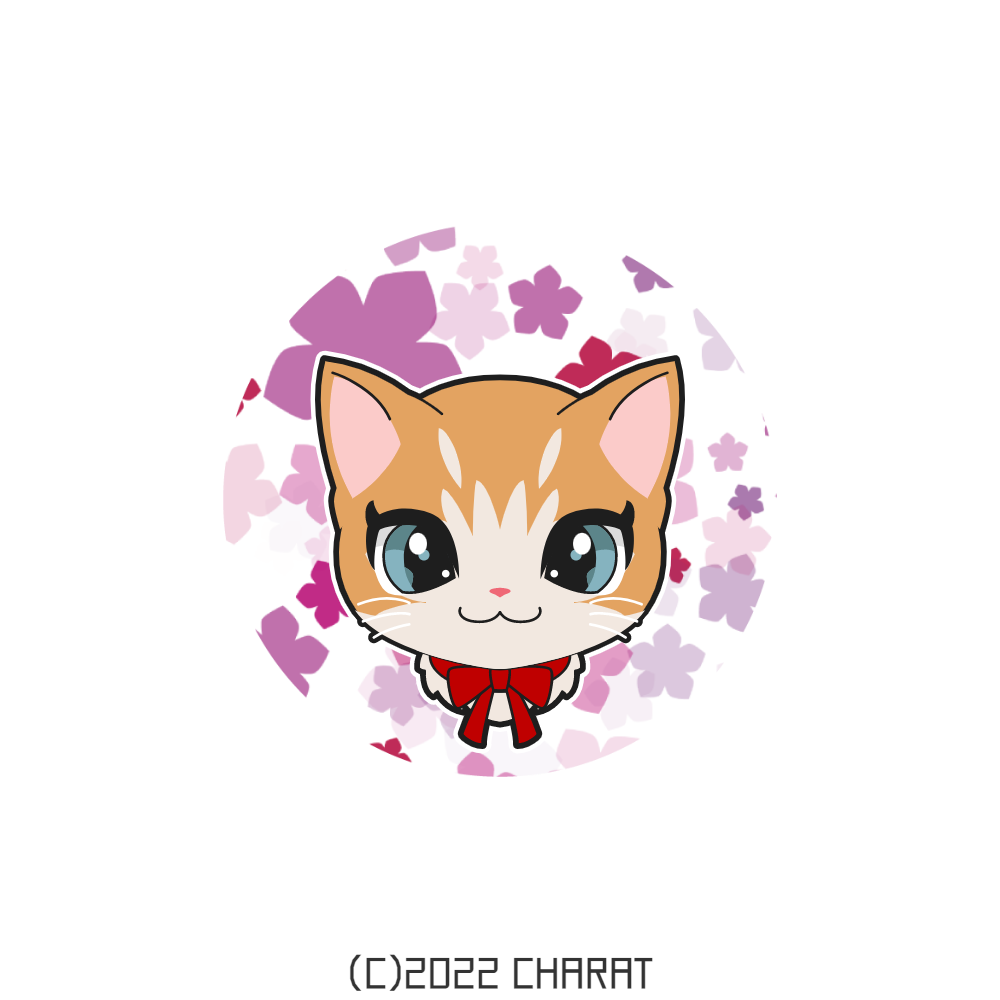
つーか普通のことしか言ってませんね。わざわざ太字で強調することですか?
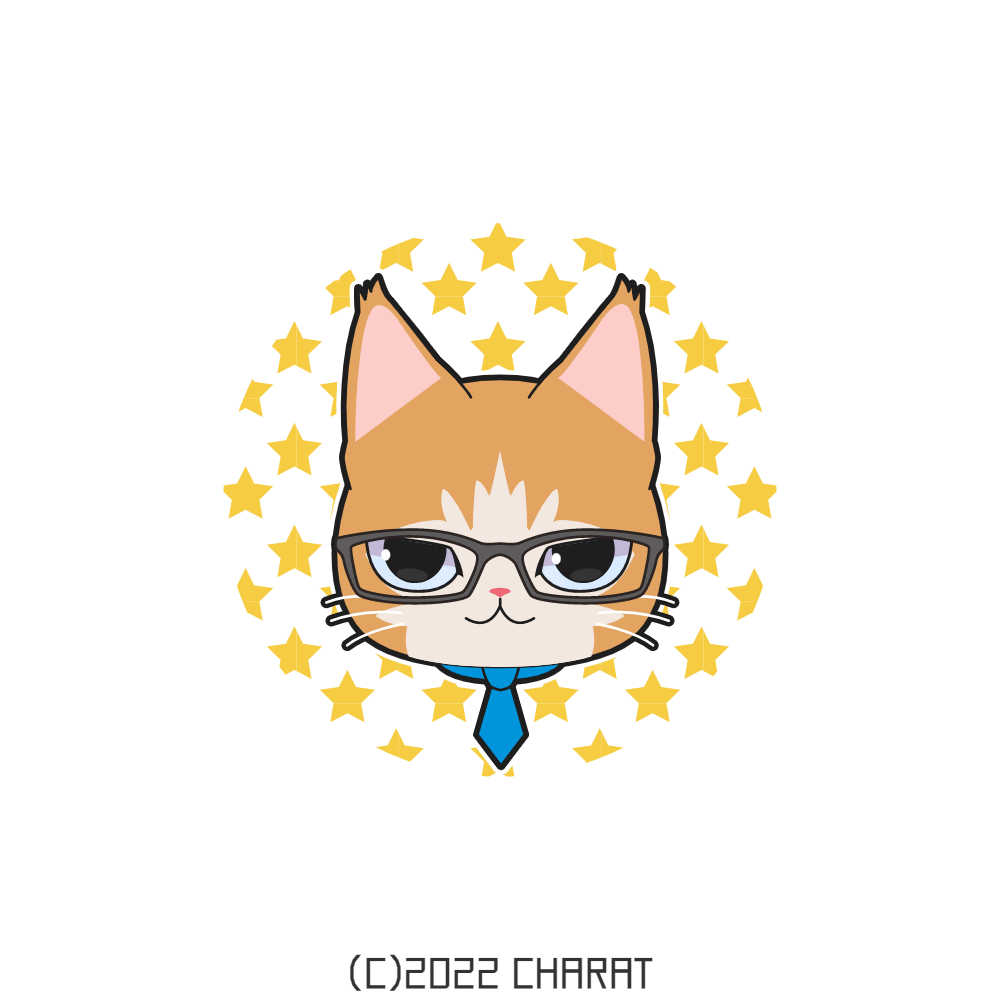
でもね、プロの目から見たら“お散歩受験”ですか?ってくらい脇がゆるゆるな対策しかしていない人が結構うじゃうじゃいるんです、はい。
大学に合格する為には、学校推薦であれ総合型選抜(AO/一般推薦)であれ、本入試でも“これを外したら絶対に落ちる”というポイントがあります。
逆を言えば、“戦略をもって実力を鍛えれば、限りなく合格に近づくことができる”
ということです。
一般的には、“これさえやっておけば志望校に絶対合格!”というのはあり得ないと言われていますし、大多数の受験生を対象にした受験情報誌や合格マニュアル、受験サイトなんかでも、大まかなガイドラインを示して、「後は自分に合ったやり方にアレンジして下さいネ♪」なんて、軽く無難に締めくくってますね。
とはいえ、一昔前に比べてネットでこれだけ受験情報が公開されているだけでも相当親切な方だと思います。
まあでも、ぶっちゃけ受験生の皆さんが一番聞きたいことは
ってことじゃないでしょうか?
学習時間・教科の管理方法について
ベネッセなどのデータでは、
と言われています。
また、一般的に毎日の家庭学習の時間は「学年+1時間が目安」と言われています。
この通りに計算してみると、
あわせて3,285時間になります。
塾長自身の実経験と肌感覚だと、
2次試験対策(すべて記述式)もあるのでこれは当然です。
いろいろなサイトで挙げられているデータを総括すると、2,500時間以上は必要です。
念のために付け加えておきますが、上記に学校での学習時間や宿題をこなす時間は含まれていません。
まさかと思われるかもしれませんけど、たまに本気で聞いてくる生徒がいるので…。
それとは別に、高校までの範囲で取りこぼしや極端な苦手分野があれば、さかのぼってさらに学習をしなければなりません。
国公立大学の推薦比率は22%でどんどん高くはなっていますが、約8割は一般入試、つまり実力勝負ということになります。
私立大学は総合型・学校推薦型選抜が入学者の割合は55.2%まで増えました。
でも45%は一般入試になります。
塾長がこれまで見てきた経験では、国公立大学・難関私立大学の総合型・学校推薦型選抜はやはり狭き門です。
自分が必ず学校推薦をもらえるわけでもないですし、総合型選抜でも合格するとは限りません。
やはり、秋までの総合型・AO選抜で、滑り止めを確保しつつ、本命である、人気・難関校は一般入試が多い印象です。
少し哲学的になりますが、確かに、世の中で「絶対」はないと思います。
例えばよくある感動もので、“絶対に無理と言われた大学に奇跡の合格”というケースも、大学受験生約50万人の中で100人もいないはずです。
100÷500000=0.0002%、つまり1万人に2人の確率です。
これを読まれている皆さんの知り合い・同級生を含めておそらく一人も見当たらないということになる確率です。
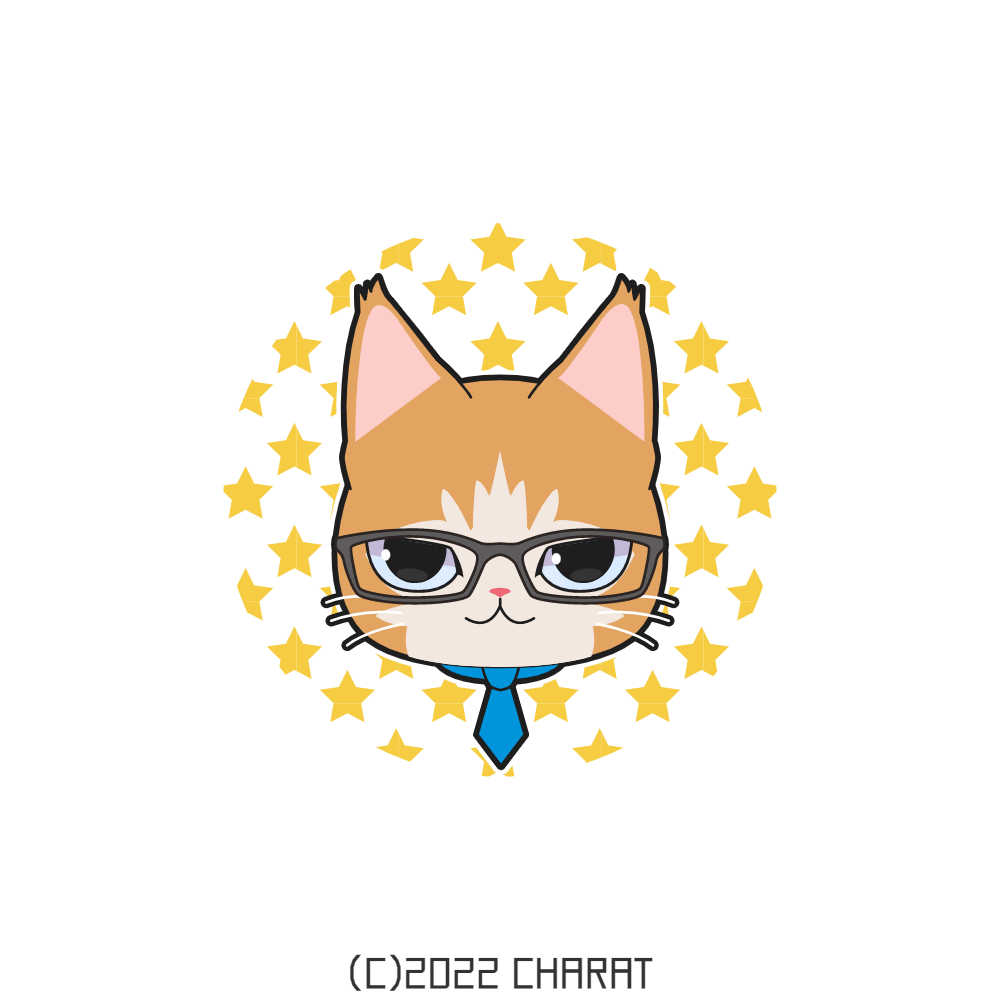
正味100人でもかなり多いかなと思います。実際はもっと少ない印象ですね…。

こういった内容のものは、書籍やテレビ、映画などでよく取り上げられます。
しかし、なぜ大勢の人が好んで見るのかというと、日常でほぼ起きない奇跡的事実に感動したり、カタルシスを感じるからだと思います。
奇跡や感動ものには、現実だったら不合格だった、こうあってほしかったなどという願望が投影されているからこそ、勇気や元気をもらったりするわけです。
本気で志望校を目指している高校生の皆さんなら、きっともう客観的に考えられると思いますが、
「のんびり好きな事だけをして暮らしていたら、いつの間にか自分だけ学力がアップして、ラクラク志望校に合格していました。」というよくある転生ものみたいな話は夢どころか妄想であり、
「約50万人の受験生の一人である自分に都合のいい奇跡はほぼ起きない。」
ことを本当は良く分かっていると思います。
できれば楽していい目にあいたい。なるべく努力を減らして人気の高い大学に入りたい。
皆がそう願うからこそ、そこに厳しい競争が生まれます。
浪人生がどんどん減少し、受験生全員が大学に入れる時代になりました。
ですが、誰でも目指せるようになったことで、人気のある大学や難関大学の競争率は高いままであると最近のニュースでもありました。
昔も今も変わらず、希望する大学に合格する為にはやはり「正当な努力」が必要になります。
これは社会に出ても変わりません。
ですので、今後もこの講座では、「正当な努力」を前提として話を進めていきます。
実を言うと、チートな裏技がないこともありませんが、ここでは扱いません。
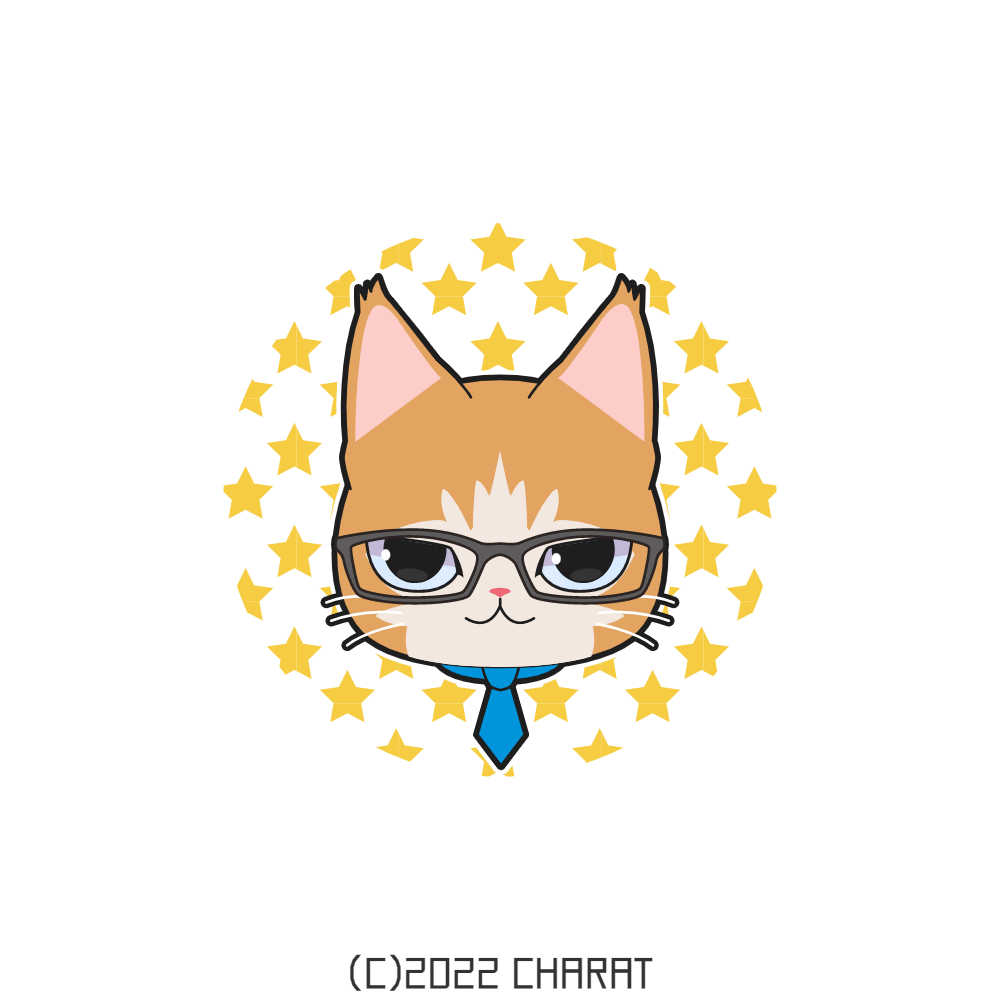
たとえ50ccの原チャリに高性能な加速エンジンをつけてもらったとしても、自分自身でうまく使いこなせないなら意味がないですし、そうやって楽やズルをして大学に入学しても、ペラッペラの張りぼての実力では進級や就職、その先の人生まで通用しないですよ。
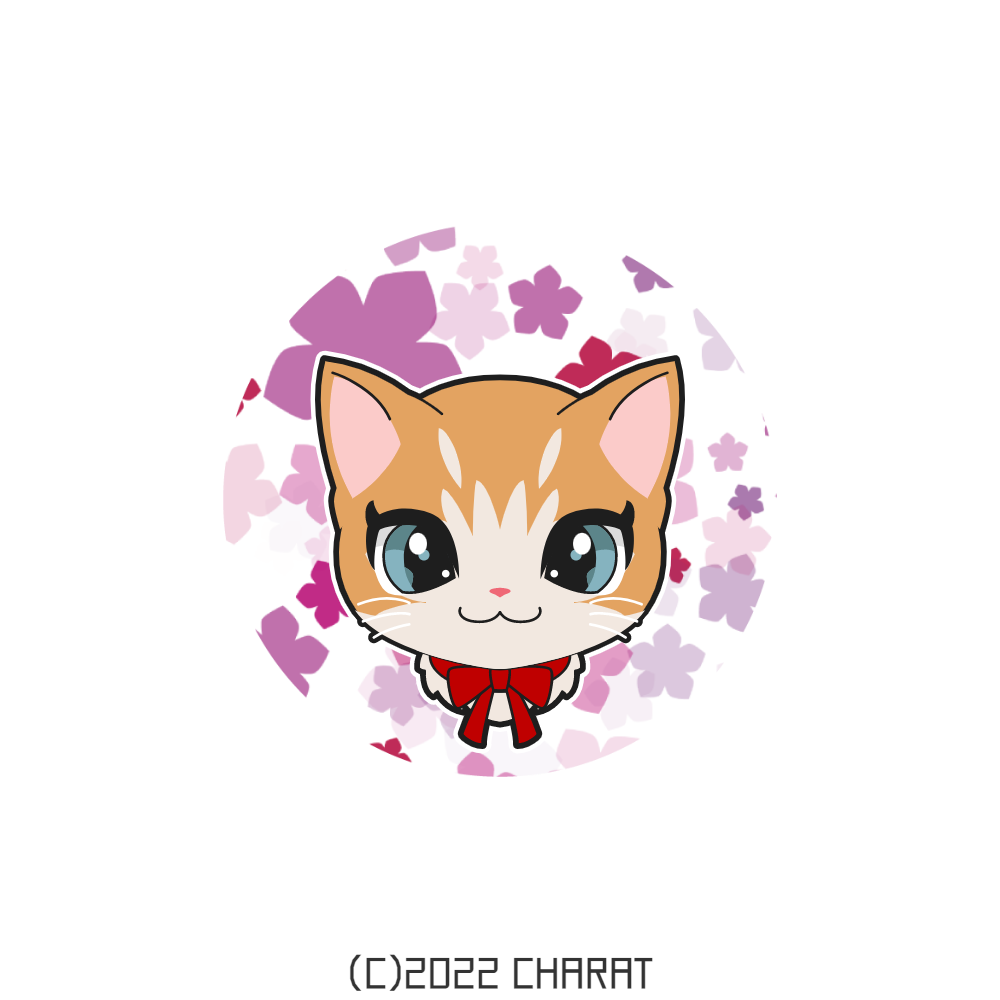
と言いつつ、そのうち塾長はうっかりポロっとどこかで漏らしますよ、たぶん。
とりあえず、「正当な努力」と聞いて、心底ガッカリしている人に朗報です。

いくら努力しても、見当違いのことばかりしていては時間を浪費するだけです。
この講座では、無駄な回り道をして迷宮に入らずに効率よく合格を目指す方法をできるだけわかりやすくぶっちゃけながらお伝えしていきたいと思います。
ただそうは言っても、最終的には個人個人、得意不得意も志望校・学科も違うのでやっぱりオリジナルのアレンジは必要になります。
一般入試で合格するには
大学入試は、教科書の学習だけでは合格できないことは、誰でもわかると思います。
私立中高一貫校や進学校では学校配布の参考書・問題集もかなり手厚いですが、
受験は一人一人違うので、実践問題集・過去問題などはどうしても購入しなくてはなりません。
予備校・塾に全て任せるのも一つの手段です。
しかし、予備校は個人にフィットするものを選んでくれるわけではありません。
そこで、なるべく無駄なく合格できると思われる参考書・問題集の選び方をご紹介したいと思います。
まず、今回は「一般入試で合格する」ことを目的に書き進めていきます。
冒頭でも述べたように、最終目標(志望する大学に合格すること)にたどり着くには、正しい道を示す地図の内容が間違っていては目的地につきません。
その地図の一つに当たるのが、“テキスト・問題集の選び方”だと思います。
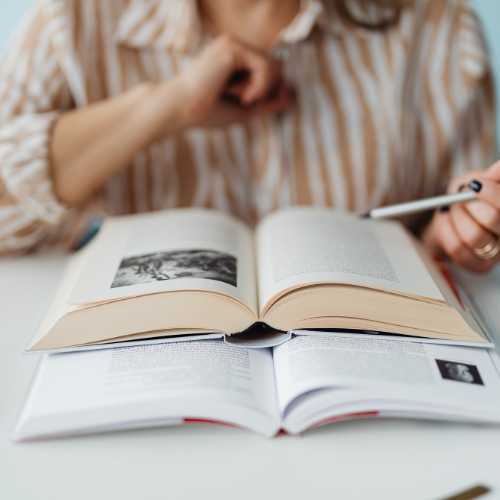
学校の先生、予備校・塾の先生、家庭教師、大学生、友人・先輩などに聞いてみましょう。
同じ学校なら学力レベルは近いはずなので参考になります。
ネット、受験雑誌、本などです。
一人でも探してみたり、友人たちとも行ってみたりして意見交換しましょう。
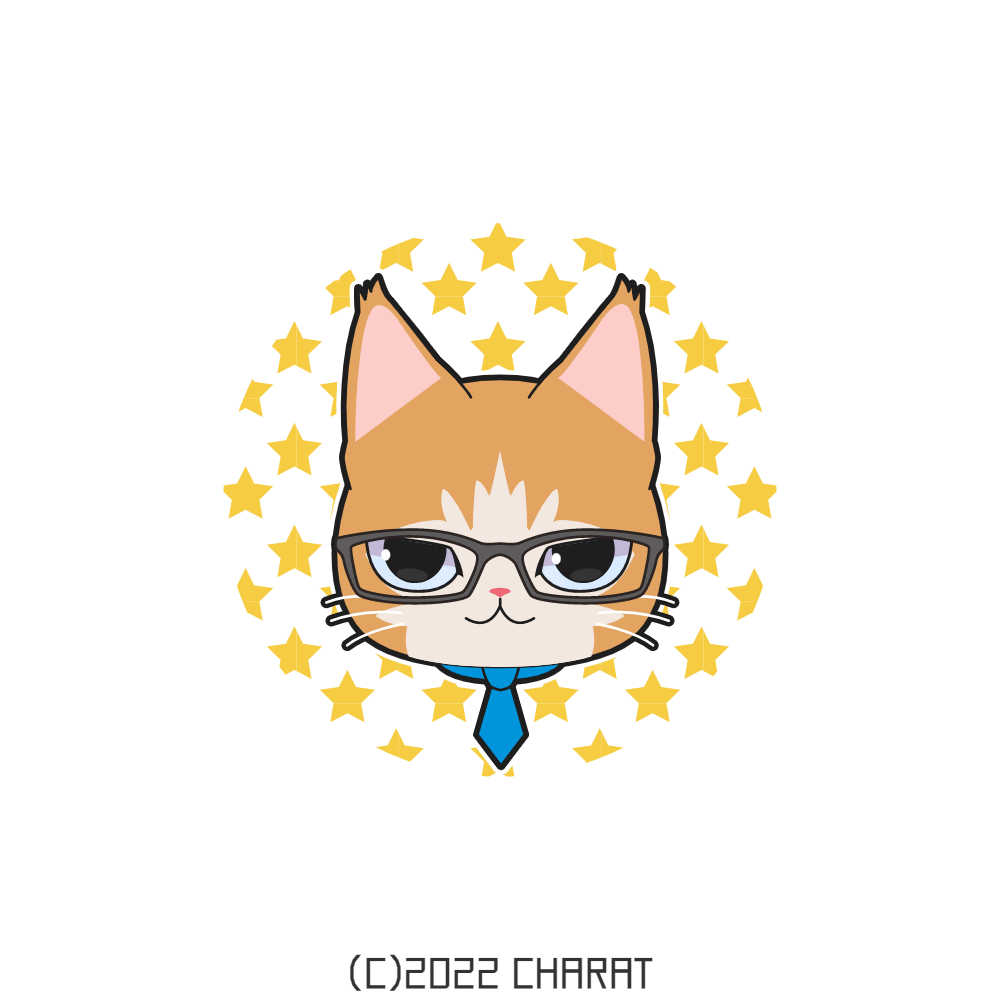
テキスト・参考集の選び方を簡単にまとめると、
「人に直接聞く」か「間接的に調べる」になります。
やっぱり普通のことしか言ってないじゃん、と思ったそこのアナタ、
次回はさらにもっと深堀りしてお伝えしていきたいと思います。