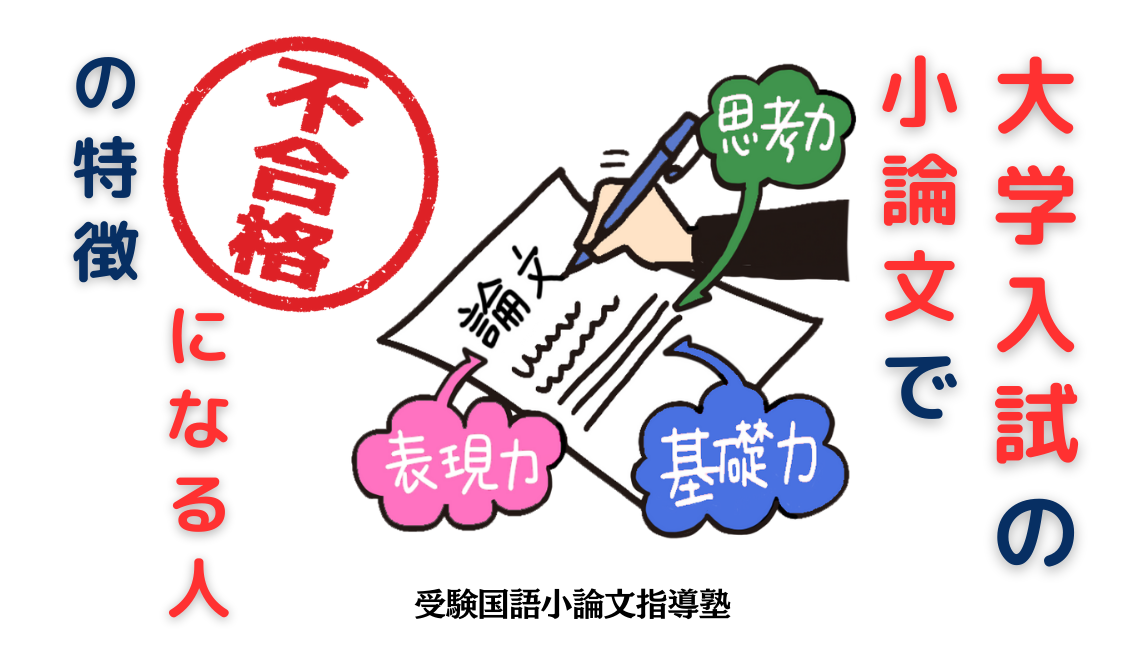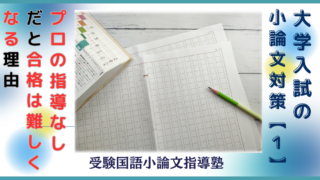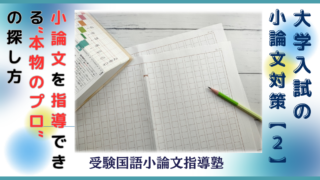大学入試の小論文対策について、学校や塾、予備校等で指導を受けている人・自力で練習している人、両方いると思います。
いずれにしても、自分では何も考えず誰かに丸投げで努力を怠れば上達するわけはありません。
今回は、小論文入試でなるべく不合格にならないためのヒントをお教えします。
実際に指導してきた中で気づいた”不合格になりやすい生徒”の特長

自分独自の実体験や解答パターンを持つのは非常に心強いですが、その一本槍だけで合格するほど甘くありません。
フットワーク・知識・文章力は必要です。
書き直しを嫌がる生徒がほとんどです。最難関校は書き直しをしないでは、とても受かると思えません。
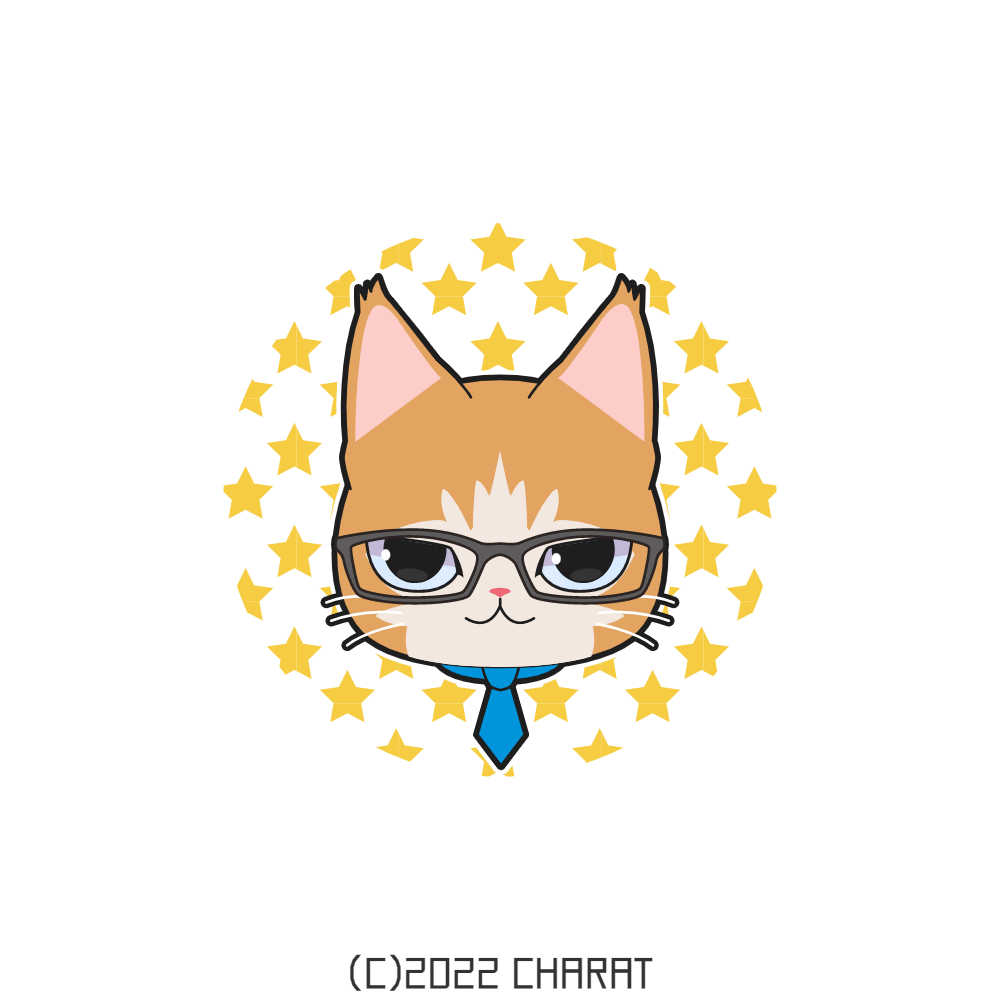
「書き直した方がいいよ」このセリフ、今まで何百回言ったことでしょう…。
親御さんは知っているのか知らないのかわかりませんが、たとえ学校の内申点が良くても9割近くの生徒が聞き流して書き直しをしません。
これが”現実”です。
費用を無駄にしたくない親御さんは、一度我が子に小論文の書き直しをしているか尋ねた後、指導している先生にも確認してみてください。
ある程度書けるようになって余裕ができたのか、それとも急に自我に目覚めて自己主張したくなったのか、出題テーマに対して挑むような、採点者の反感を買うような文章を書く人がたまにいます。
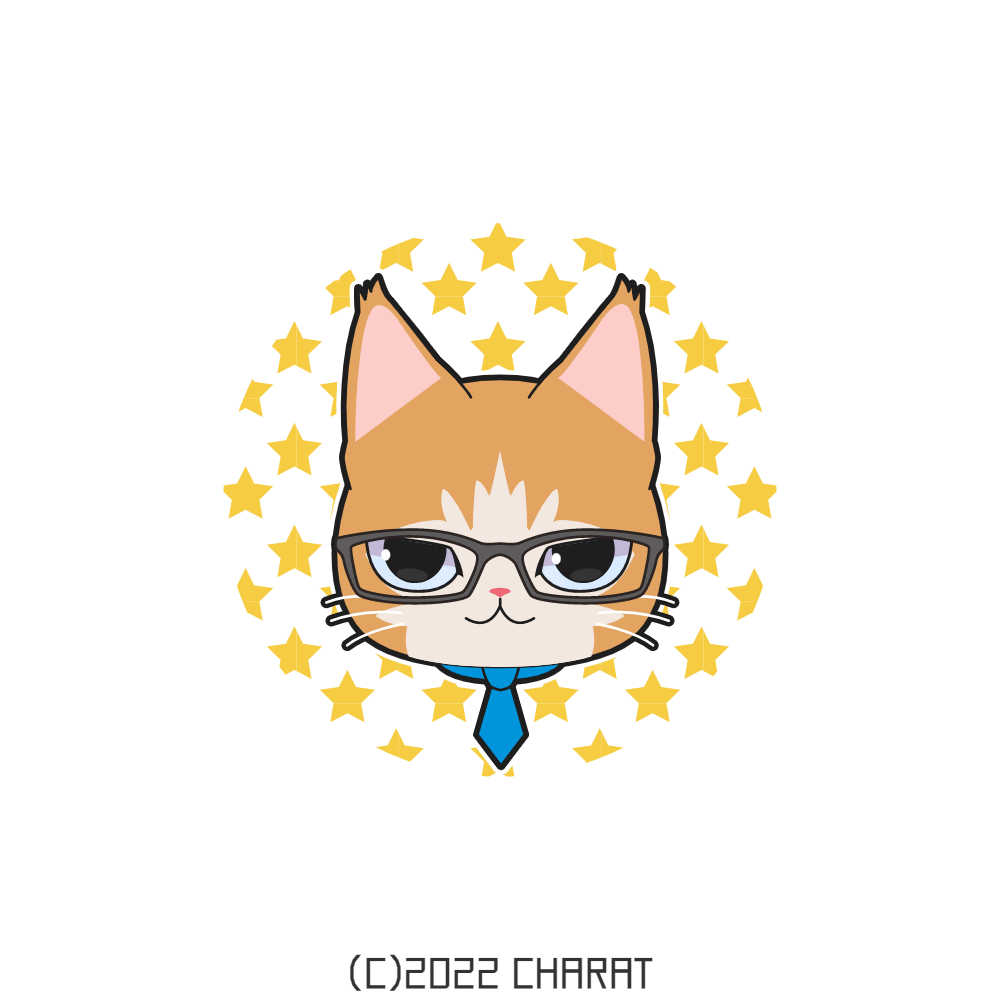
採点者目線からすると、知識も足りない上に専門家でもない人間が得意げに論じている姿ほど滑稽なことはありません。
下記のページでも既に書いていますが、中身のない文章をだらだら書き続けたところで身になるどころか悪い癖がつくだけで時間の無駄になります。
長期間、実力のない指導者のもとで学んできたせいか、どうしても文章の悪い癖が抜けない人がいます。
実力のない指導者に学ぶ弊害については下記にも詳しく書いています。
「~だ」という断定表現をよく使う人がたまにいます。例え断定で書いても、内容が素晴らしければ大変説得力があります。
しかし、見当違いな内容だったり、浅い知識で述べていたりする文章(大半の生徒に当てはまる)は、採点者から良い印象は得られません。
ただでさえミス(間違いや浅い知識)があるだけで減点されるのに、断定することで評価がより下がる可能性は高いです。
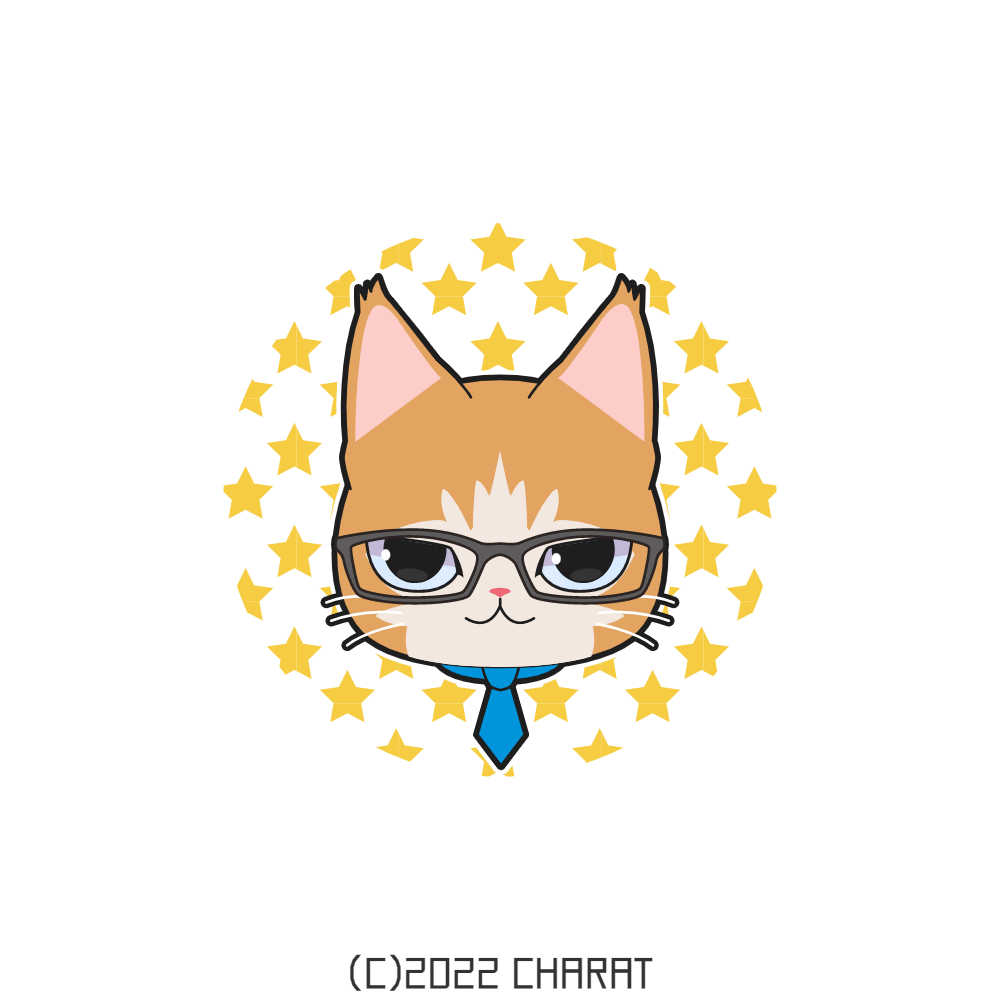
何十年も同じ内容で出版されているテキストでは断定口調を推奨しているものもあるようですが、塾長個人としては”時代遅れ”だと思っています。