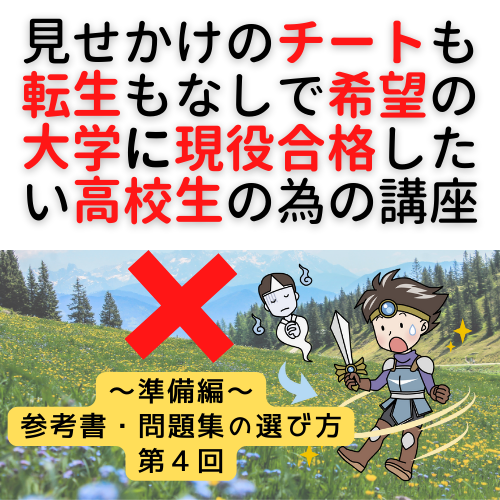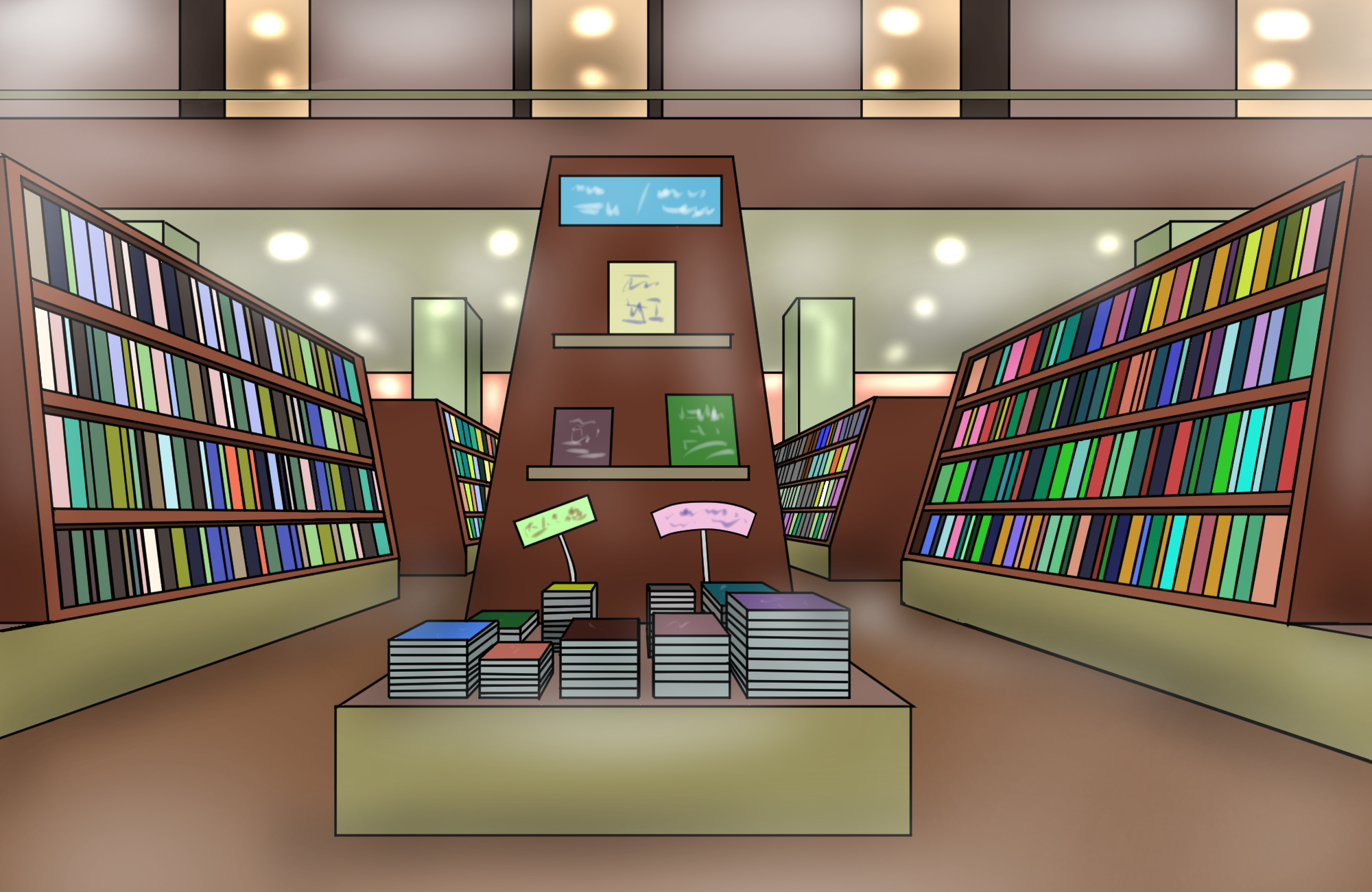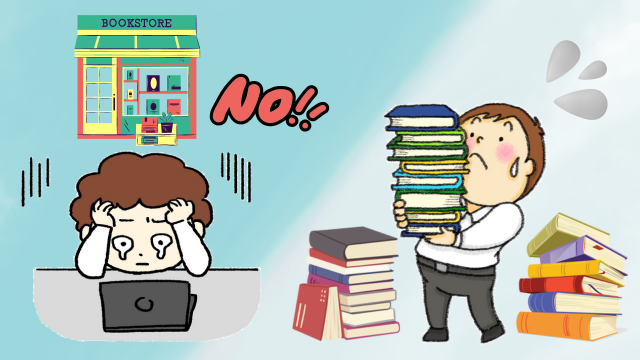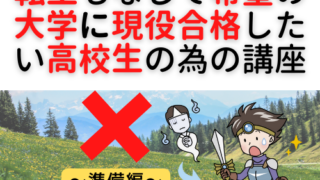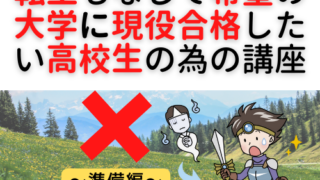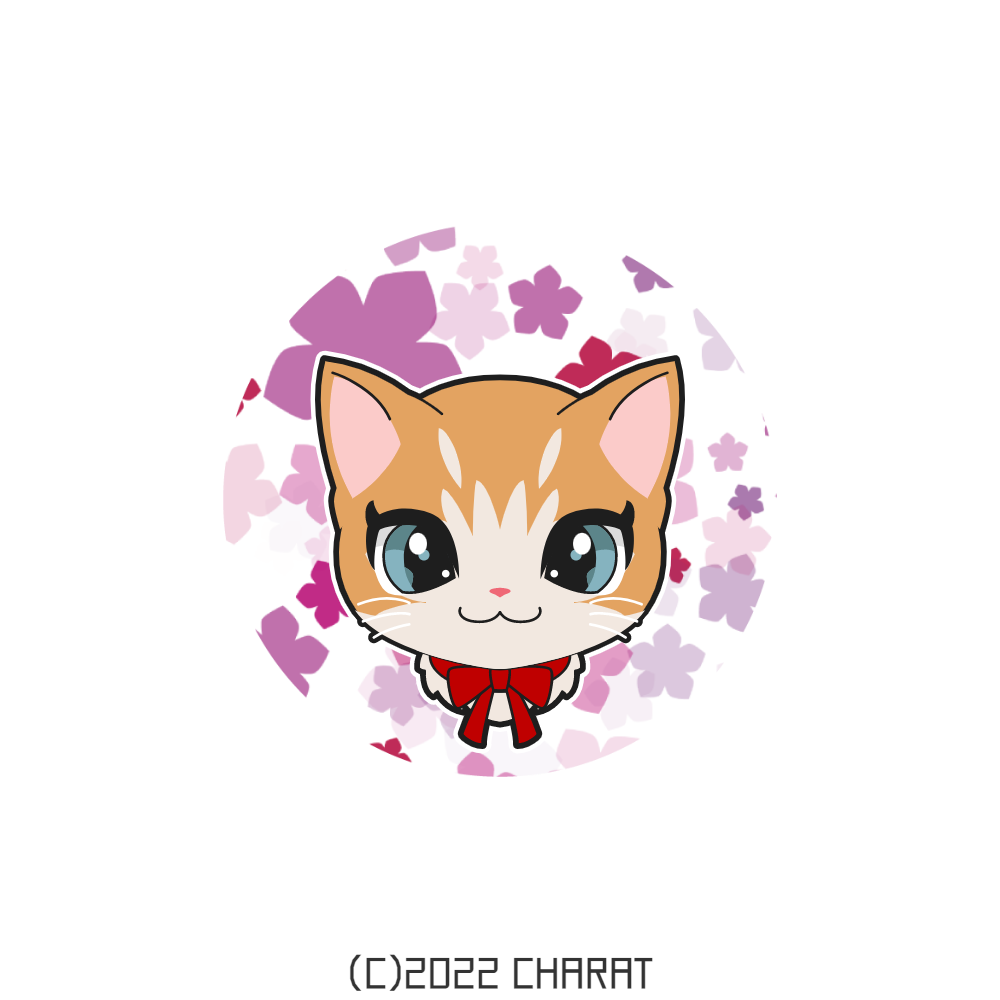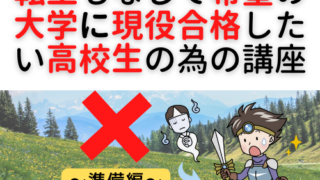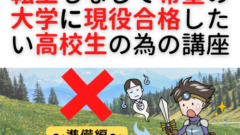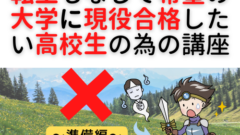書店に行って探す
ネットも便利ですが、実際に書店に行って、中を確認してからじっくり検討しましょう。
定期試験前や受験期は、梅田の丸善ジュンクや天王寺の書店で高校生が問題集・参考書を選んでいる場面を頻繁に見かけます。
塾長が学生の時も、試験が近づくと不安にかられて本屋に行ってはなんやかんや購入してしまっていたので気持ちはよく分かります。
テキスト選びはまず一人で行く方がお勧め
都市部や主要駅の近くに住んだり通学している場合、大型書店があります。
この場合、足を運んでテキストを検討することが出来ます。
※地方で小さな本屋しかない、本屋すらないケースは後で述べます。
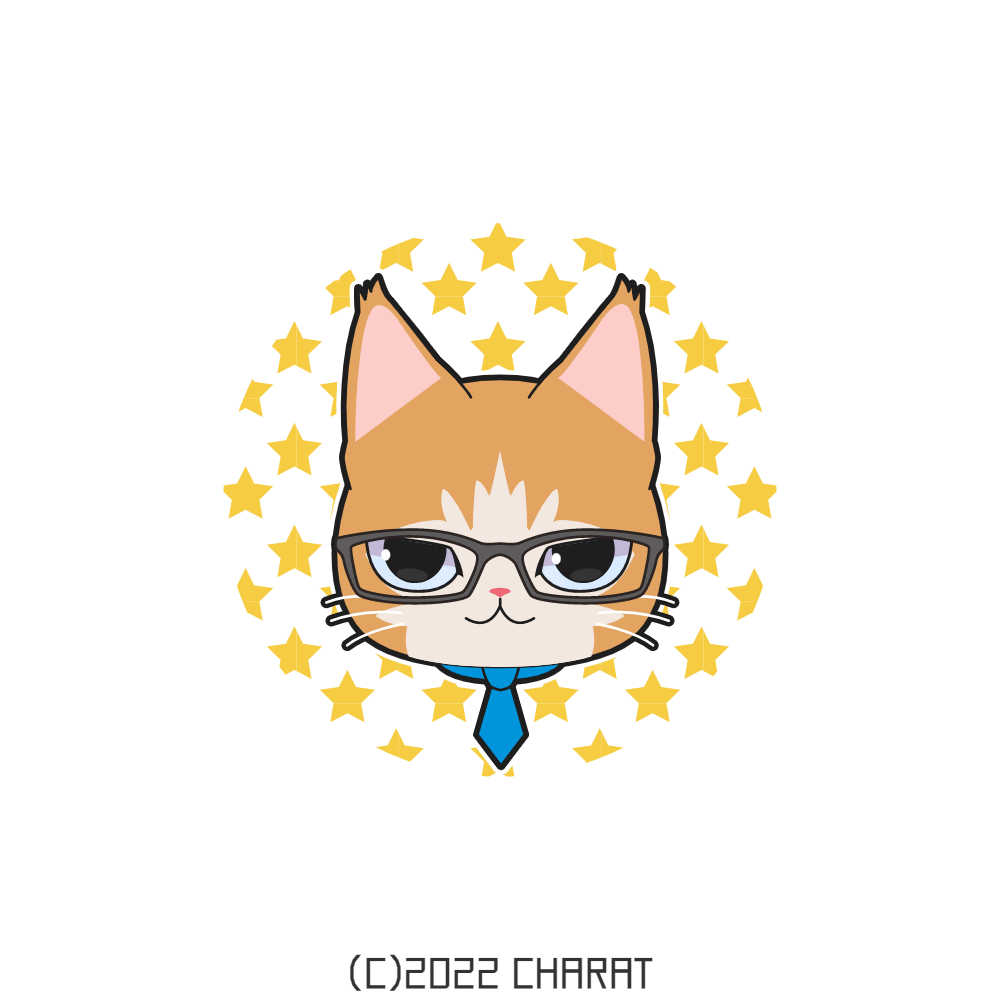
まとめて購入して、一定金額以上(7,000円~1万円)なら無料で宅配にしてくれます。
塾長も5冊以上購入して持ち歩くことがありますが、肩が砕けそうになるし、エコバッグが裂けて破れたことが何度かあります。
何も調べていなくても、とりあえず一人で本屋に行ってみましょう。
そして、売れ筋や平積みされたりするものから選びましょう。
友人と一緒に行くと、ついつい他人の意見に引っ張られ、購入後に「やはり合わなかった」「簡単すぎた」逆に「難しすぎた」などということがよくあります。
特に、優秀な友人だった場合、内容が難しければ難しいほど良いテキストだと思い、自分の今の実力では歯が立たなかったというケースはありがちだと思います。
テキストを選ぶための自分軸を作る
どれほど仲の良い友人であっても、受験情報を交換するのも限界があります。
なぜなら、それぞれ志望校、得意不得意や受験教科などが違うからです。
地方で地元志向だと選択肢が狭いので志望校が一致するケースは多いと思います。
実際、塾長の田舎もそうでした。
しかしそれでも、基本の共通教材を除くと、おのおのに向いた参考書・問題集は違うものを使っていました。
上記のように、得意不得意・受験教科が違うからです。
まずは、
- とりあえず一人で検討して自分の中に軸を作る
- 友人たちと行き検討する
という順番で購入することをお勧めします。
参考書なら詳しい用語・特殊項目をメモして、それが載っているかどうかで詳しさの尺度になります。
これは、古語辞典や英語・ドイツ語など、辞書・事典を選ぶ時の基準と同じです。
塾長自身も大学院で使用していた「英和中辞典」(大学入試レベルではとても足りません。)はこの基準で選びました。
参考書・問題集も同じで、簡単すぎても難解すぎても役に立ちません。
自分のレベルでもついていけて実力アップに繋がるものを選んで下さい。
家庭教師・個別指導・少人数塾などの指導を受けていないのなら、どこが出来てどこでつまづいているのかが分かるのは自分しかいません。
自分軸ができた後に他者と様々な意見を交換することで、外れテキストを購入してしまうリスクはかなり減ると思います。
「三人寄れば文殊の知恵」とはよく言ったもので、実力やレベルが近いらしい学生同士が相談しながら一緒に選んでいるのをよく見かけますが、明らかに外れと思えるテキストは選んでないようでした。
同じ学力の友人と話すと思わぬ気づきがあったりします。
自分も苦手な分野に詳しい・わかりやすい参考書を教えてくれたり、偏差値アップに効果的な問題集を持っていたりします。
前述したように、本当にいい参考書・問題集でも全く歯が立たないケースは多いと思います。
なぜなら、高い目標にばかり目がいってどうしても背伸びしがちだったり、教師・講師目線で選んだものはレベルが高かったりするからです。
基本ができていないのに、実践問題集をこなしても実力はつきません。
ですので、自分がどの段階かをよく見て選んで下さい。
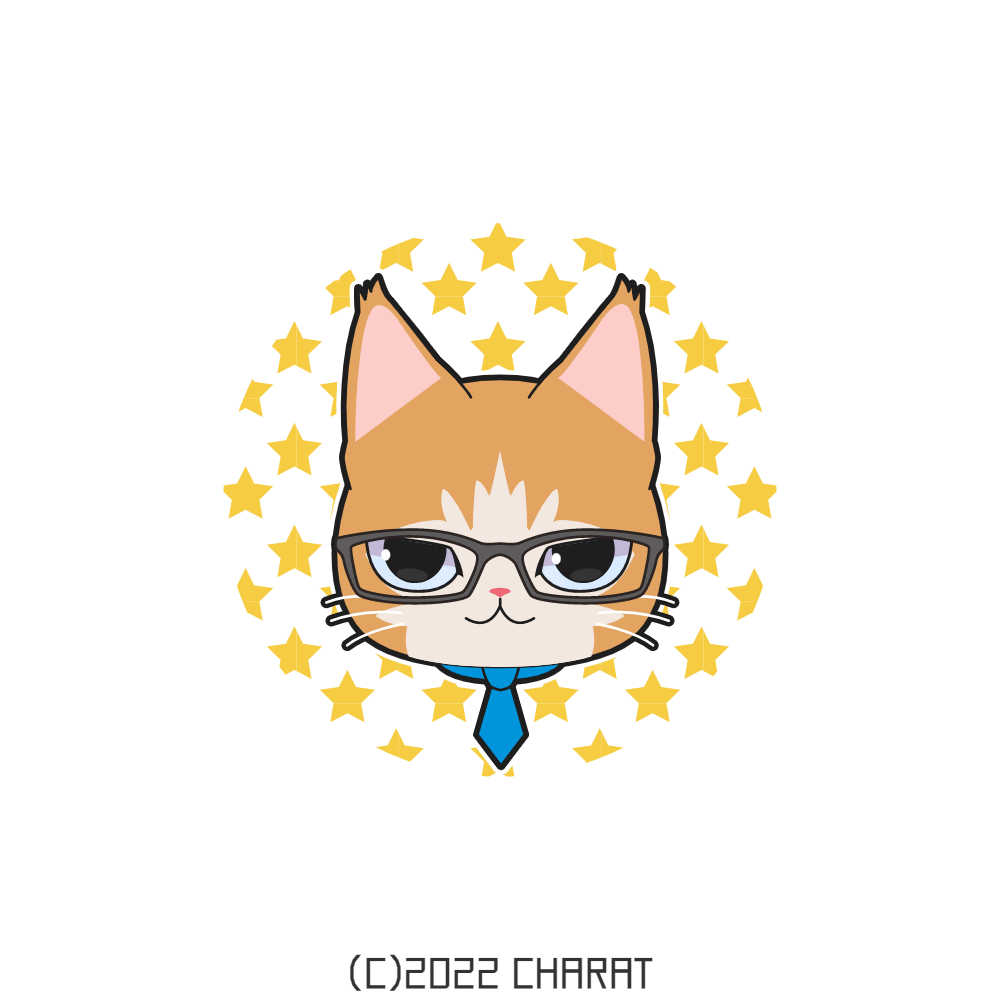
今の時点で全然歯が立たないものはまだ先の教材です。
また、8割以上出来るものはこなす必要はないでしょう。
4割~6割程度わかるものが一つの目安です。
(4割程度しか分らないと、こなすのに相当苦労はしますが…。)
受験雑誌・情報誌を活用する
専門受験雑誌も参考になります。きちんと販売されているものは信頼性が高いです。
有名なのは「蛍雪時代」です。
この雑誌の受験データはいまだに必要で塾長も購入しています。
お勧めの参考書・問題集も掲載されています。
欠点は自社のものしか載っていないことです。こちらは各予備校や大手書店に置いてあります。
中学入試・高校入試・大学入試や数学専門誌など色々あります。
また、大手予備校のフリーペーパーも活用できます。
無料でも大手出版社や大手予備校のものは宣伝色が強いですが、内容はきちんとしています。
とはいえ、情報誌は有料のものほど確実です。
有料だからこそ、情報の信頼度が低いとクレームが入るからです。
しかし、たとえ有料でも塾や予備校が販売しているものは、その塾・予備校のカラーが強いので割り引いてニュートラルに検討して下さい。
結局は、ただ自分に必要かどうか、合うか合わないかです。
近隣に大きな書店がない場合
大きい書店、参考書・問題集が充実してる書店は都市部に集中しています。
たとえ都市部に住んでいたとしても、大きな本屋のすぐ近隣に住んでいる人は少ないと思います。
近くに大きな書店がない場合、ネットでいきなり購入するしかありません。
ですが、ネットだと中身がみられず、関係ないものも大量にでてきて判断するのに非常に手間がかかり、結構疲れます。
現物を手にとってチェックできず、テキストが当たるまで購入し続けなければなりません。
※塾長がかつてそうでした。この話はまた次回に書きます。
「メディアで探す」でも書いたように、アマゾンでも売れ筋ランキングがありますが、或る程度参考になります。
一から学習を始める段階なら外れることはないはずです。だって定番ですから。
サイトを厳選して、アマゾンなどで試し読みをして、他の人達のレビューを参考にして間違いないと思って購入しても、実際に手に取ると「ハズレ!」なんてことは良くあります。
こればっかりはもう仕方ないです。
でも、交通費だけで数千~何万円も使って都市部まで足を運んで選ぶよりは損害は少ないです。
関東の都市部在住の方のブログで、わが子の中学入試で塾以外のテキストを購入されていましたが、
約30万円購入して実際に使えたのは10万円分、つまり1/3の確率でした。
こちらは成功したケースで、最難関校に合格されていました。
塾長の場合ですと、大学入試の際は段ボール3箱(約10万円)購入して、やはり1/3位(段ボール1箱)をヘビロテして学習しました。
田舎出身な上にネットが今ほど普及していなかった為、テキストの中身も確認できずに買うしかありませんでした。
それでも、支払った10万円のうち大学合格に役立った分は約3万円なので、まあ納得できました。
ちなみに1/3という比率については、第2回の記事でも述べています。
たとえ本屋で確認して買ってみても、使用するうちに「なんか違う。」「使いにくい。」「いまいち。」なものは2/3程度はあると思っていると楽です。
国公立大学志望だと、参考書・問題集を全教科購入しようとすると、1教科につき1~3万円はかかるので、全部で10万円以上は軽く必要になるかもしれません。
なので、何回かに分けて教科ごとに購入すると負担は少ないかと思います。
学歴の集大成である大学入試は人生が掛かっていますから、
合わなかったらすっぱり使用をやめるか、学力が上がって使えるまで置いておきましょう。
そして、また足りない分野を調べて購入しましょう。
これは何でも当てはまります。読書も当たり外れがありますよね?
ホント、トライアンドエラーの繰り返しです。
そうやって良書に出会ったり見抜けるようになったりするのです。
とりあえず、
- 店員一押しのもの
- よく売れているもの
- 版を重ねている定番のもの
はそんなに外れません。もろん自分に合わないことはありますから、その中でさらに厳選してみてください。
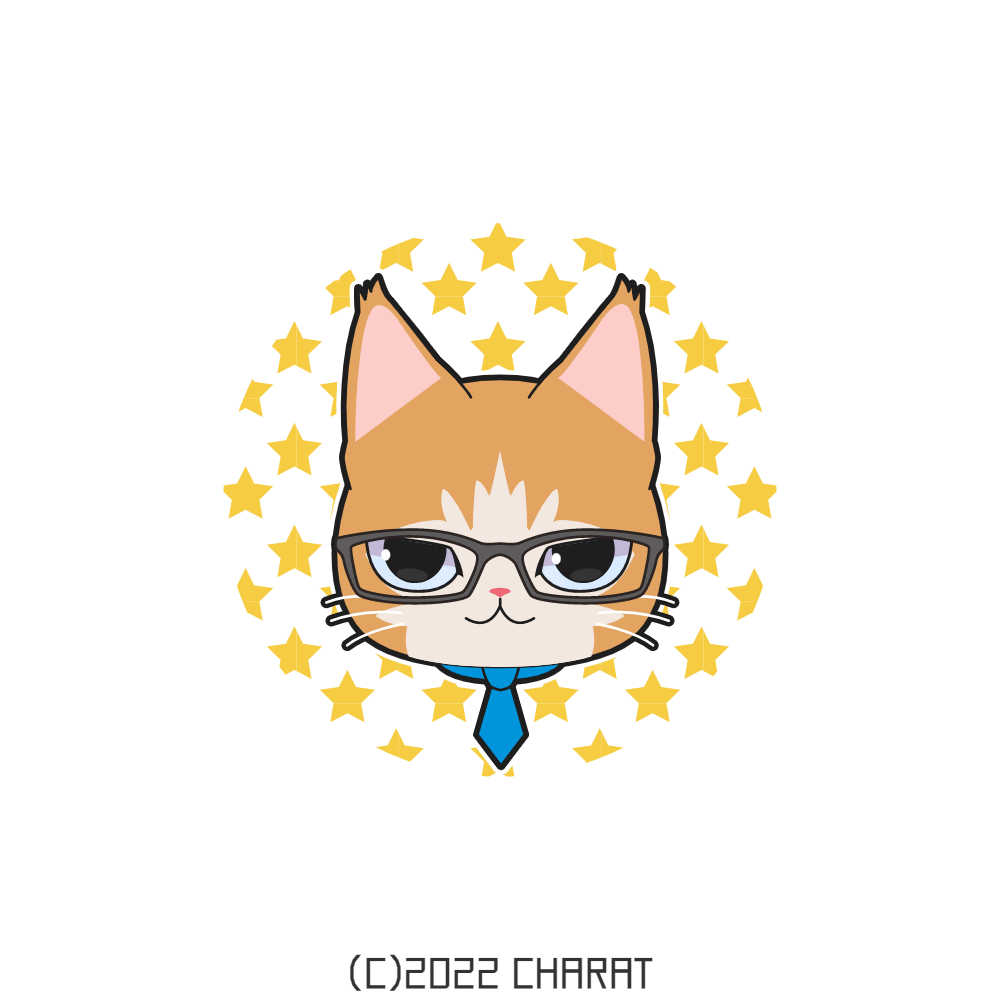
今はネットもあるので、うまく駆使することができれけば”ほぼ当たり”なんてこともあると思います。
“絶対ハズレなし!”を望む人は、プロの家庭教師か専門講師(自称はダメですよ。ちゃんと根拠のある本当の実績を出している人)にしばらく指導してもらった後に、志望校にそって選んでもらえば、量もレベルも間違いはありません。