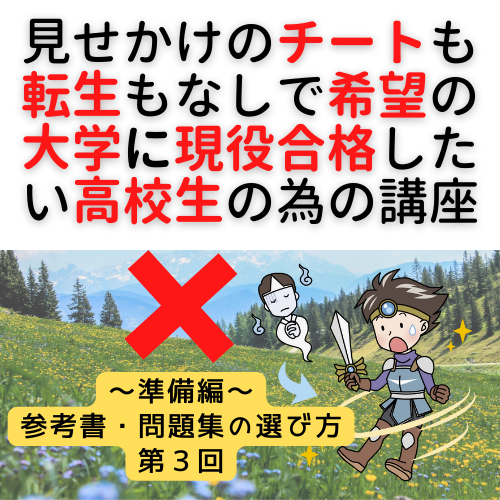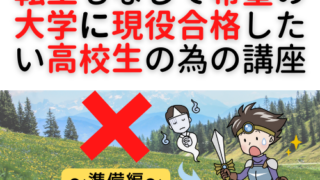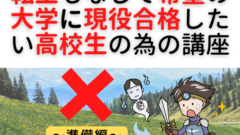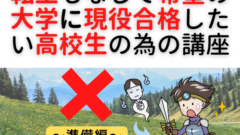ネット、メディア媒体から探す
参考書・問題集に関して現役大学生や各塾・予備校のサイトが本当にたくさんあります。
それらを、大げさでなくホント吐くほど見ましょう。
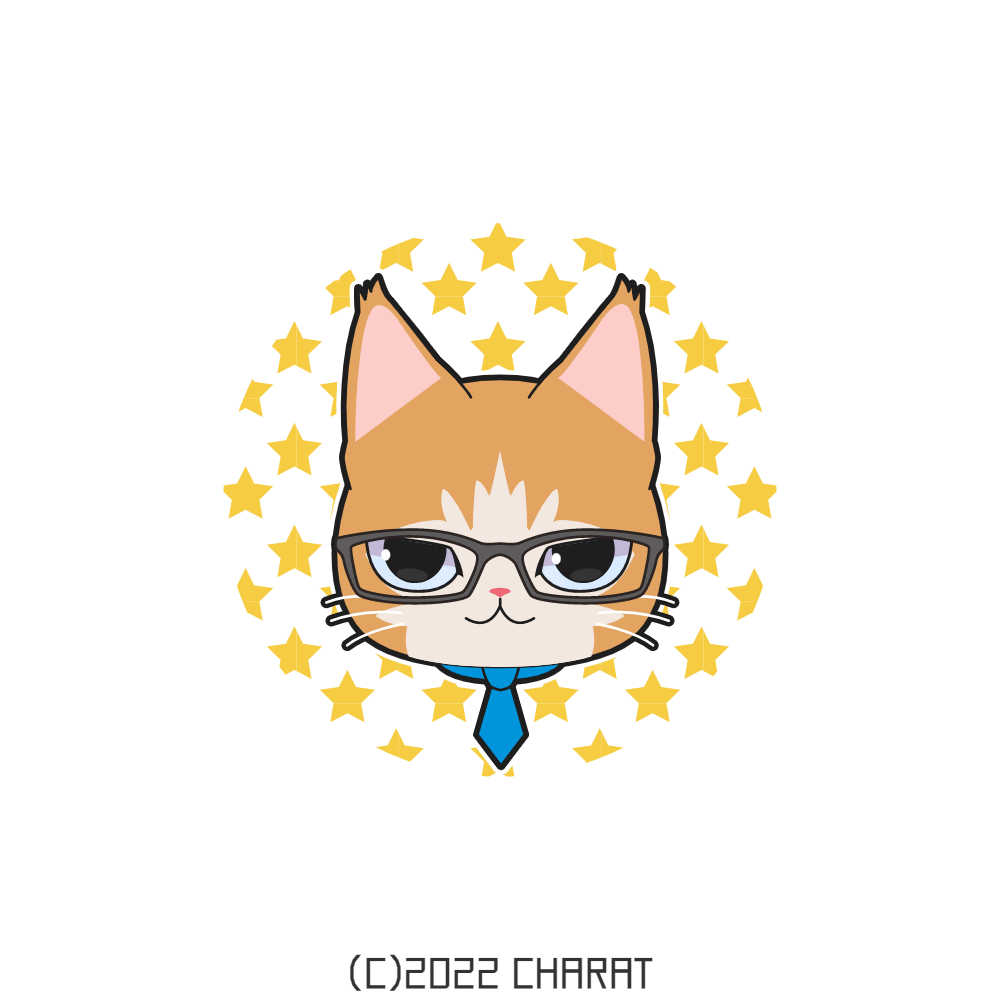
本気で探し出したらプロでさえもマジでウツ気味になってくるけど、
なるべく費用をかけずに自力受験を目指すなら、それぐらいの熱心さは必要かなと思います。
一昔前と違いネットで必要な情報はかなり得られますし、志望校そのものや周囲の環境もグーグルマップなどで見られます。
アマゾンなどのおかげでたとえ僻地でもテキスト類が入手できるようになりました。
かつては情報弱者であった地方の受験生たち(塾長もそうだった。)も必要な情報を相当手に入れられるようになり、地方と都市部の情報格差が随分縮まったと感じます。
今の10代は何でもまずネットで探すと思います。
ただネットの世界は玉石混交で、見当違いの情報や嘘も混じっています。
ですので、塾長なりの指針を書いてみたいと思います。
情報全てを”鵜呑みにしない”ことが大切
前述のように自分の志望校や学力に合わないかもしれませんし、
単純にその情報に信頼性があるかどうかが大事です。
難関・最難関大学に入学した大学生が、自分の体験をもとに学習法やテキストを勧めているサイトがたくさんあります。
もちろん大学に合格できたのは事実であり、その人にとっては有効な方法であることは間違いなく、そこに嘘はないと思います。
しかし、例えば「東大生が進めるテキスト集」が私立大学志望の生徒に全て当てはまるかというと
違うことは分かると思います。
同様に理系と文系では学習の量や深さが違うので基礎以外は当てはまらないことが多いと思います。
また、自分の志望校の大学生が勧めたからといって、得意・不得意や個性による学習法が違うので
アレンジが必要になるでしょう。
その他にも専門塾・予備校・出版社・教師などネットで大学受験に関する情報は山の様にあります。
- 自分に必要と思われる情報をかたっぱしからたくさん集めましょう。
- 集めた情報を比較検討をして、重複しているものを中心に一冊ずつ検討・精査して下さい。
「〇○だったらコレ!」というやつですね。
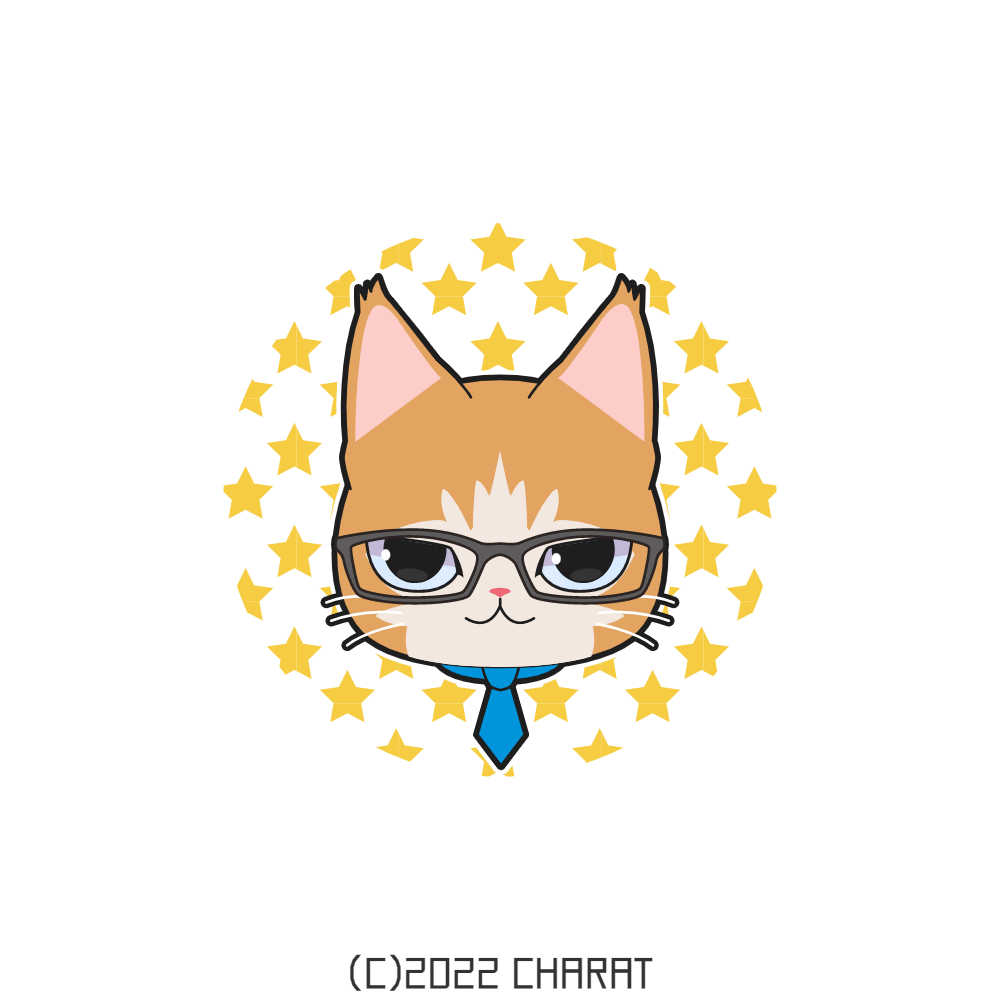
といっても、現物を見るまでは自分にとって当たりかどうか正直分かんないです。
こういった手間を惜しむ人はとても自力受験は向かないので、
正当な費用をかけてプロの指導をきちんと受けることをお勧めします。
情報サイトにしても、目が肥えないと真偽や当たりを見抜けません。
気が遠~~~くなるほどたっくさん見ていくうちに、
「このサイトは情報が浅い。とか「情報が古い。」とか「このサイトは偏っている。」
など分かってきます。
そうやって、自分に合っているサイトを見つけて下さい。
一つのサイトでしかお勧めしてなくても、自分の目標に合うか見定めましょう。
なぜなら、最難関志望や志望校が特殊だと受験者も少なく、
したがってネット情報も多くないからです。
例えば、東大についてはたくさんの情報があります。
東京にあり、日本一なので一度はあこがれて目指す人・ご家庭も多いからだと思います。
京都大学、特に理系はノーベル賞も多数でて同じく日本一といえます。
しかし、日本の首都が東京なのでやはり東京志向が高いようです。
ネットの記事によると「TVで東大の番組は視聴率がとれるが、京大ではとれないから番組が成り立たない」そうです。
クイズ番組で京大卒芸人の氏原さんが頑張っておられますが、基本的に敵役の立ち位置ですよね。
地方出身で関西在住の塾長としては、残念なお話です。
そういう訳で、東京にある「早稲田大学・慶応大学」合格に関するサイトはたくさんありますが、最難関・難関レベルでも地方の特定大学に合格する為の詳しい情報は、ごく少数を除いてあまり見られない気がします。
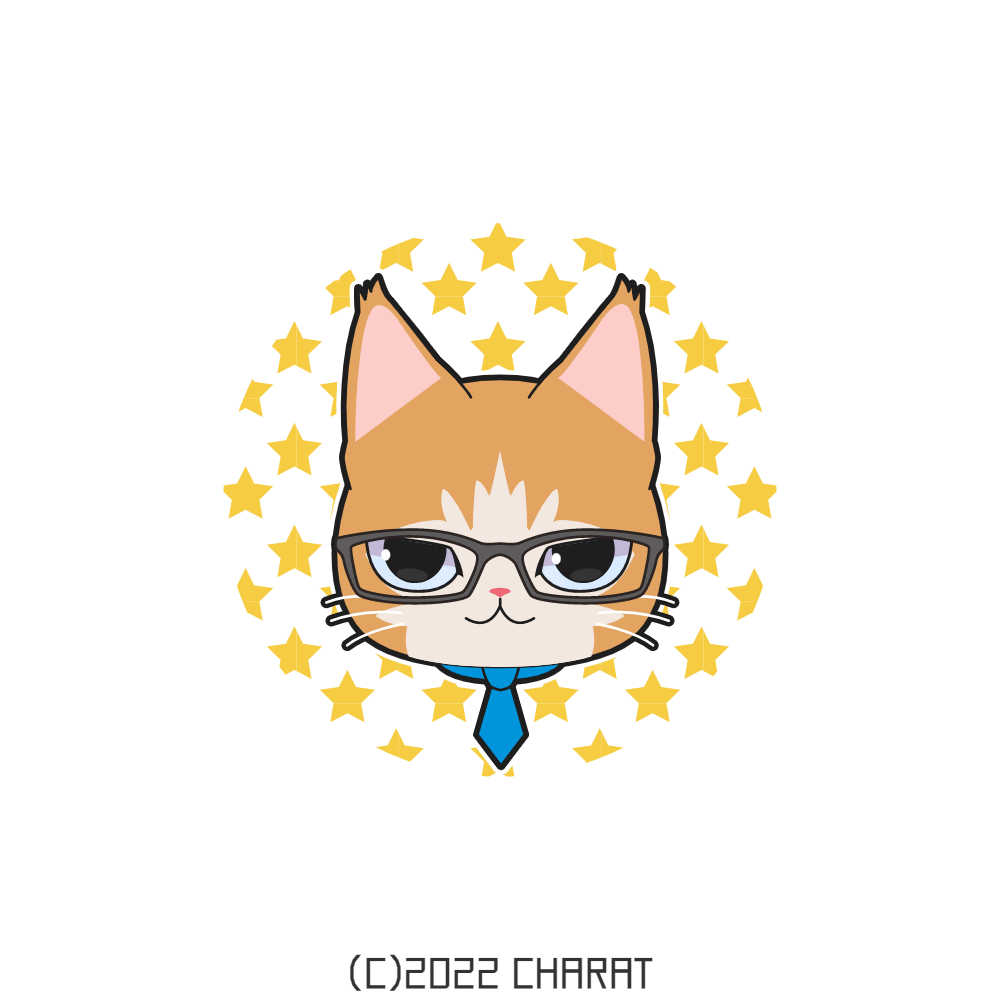
関西で有名な「関関同立」もまとめて紹介されたりしていますね。
手間を惜しまず、必要な情報は印刷する
- 内容が確実と思われるもの
- 自分に合いそうなもの
できれば、面倒でもテキストのカラー写真も合わせて印刷することをお勧めします。
塾長がプロ家庭教師時代や塾で使う市販テキストを探した時に、カラー写真がないので探すのに時間がかかった経験があります。
色だとわかりやすいですし、同じ出版社でもレベルにより緑と赤に分けていたりします。
例えば、色分けと言えば数学のチャートは有名ですよね。
「赤・白・青・緑・黄色・黒」とレベルが一目で分かります。
文庫本も作者によって色分けされている出版社(確か講談社)もあります。
ちなみに色は作者自身に選んでもらうそうです。
というように、カラー写真があると色で探しやすく間違えにくいです。
また、第二版なのか第三版なのかも一目でわかります。
と考える人が大半でしょうし、実際 改訂して新しい方が良いことが多いです。
しかし稀に、
といったことがあります。
改悪とまでは言いすぎでしょうが、
編集者がかわったのか、
もしくは文部科学省のカリキュラム改訂に合わせて簡単になってしまったり、使いにくくなってしまったり
ということがあります。
ヤフオクやアマゾンで、現在より学習内容が難しかった時の絶版になっている参考書・問題集が高値で取引されているのを見ます。
場合によっては売価の10倍以上、1万円や3万円などで売っています。
高額でもほしい人がいるからでしょう。
ちなみに、塾長の所持している参考書・問題集でも絶版で手に入らなかったり、数倍の価格になっているものがいくつかあります。
今でも必要に応じて、指導の際に使用しています。
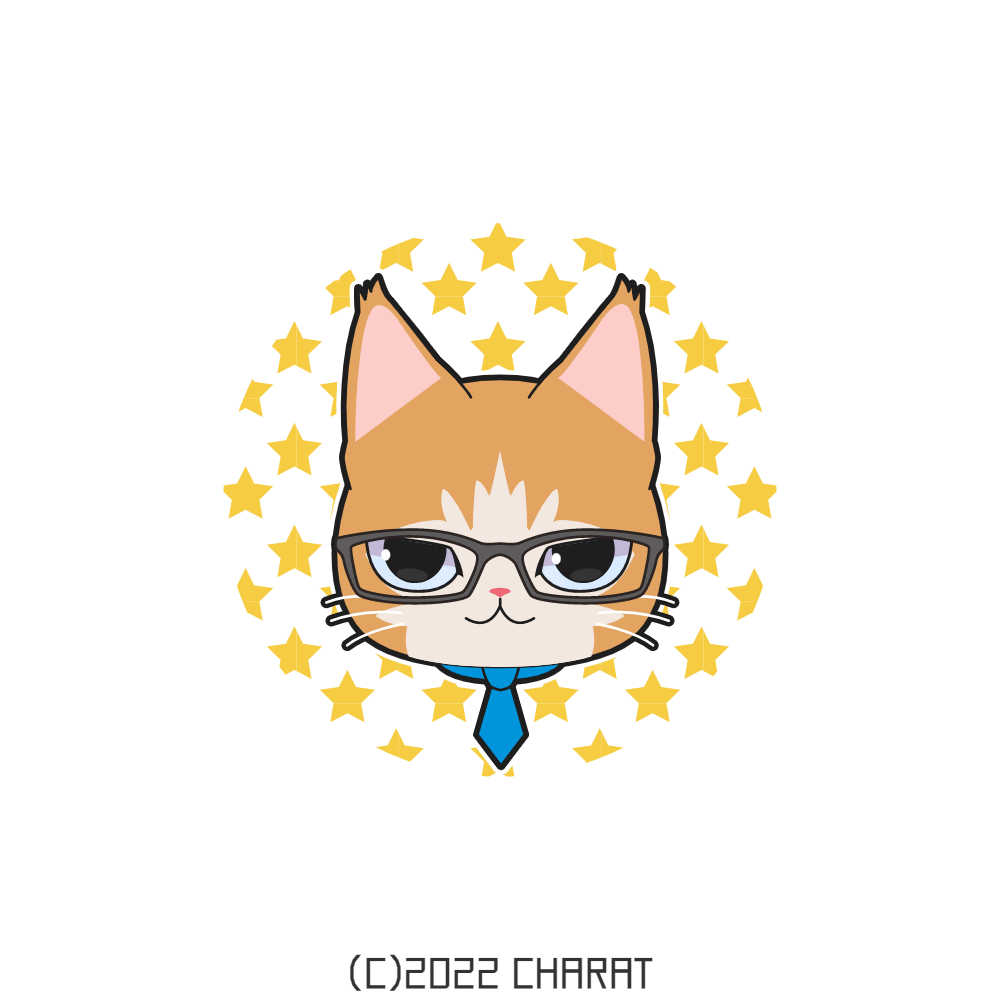
少しの違いで入試に差が出るので、手を抜かず丁寧に情報探しをしましょう。
次回、「③本屋に行き探す(実際に手に取って検討する)」です。
※テーマ3つまとめて書くつもりでしたが、思ったより長くなりそうなので分割します。