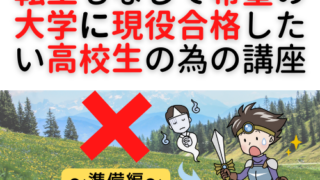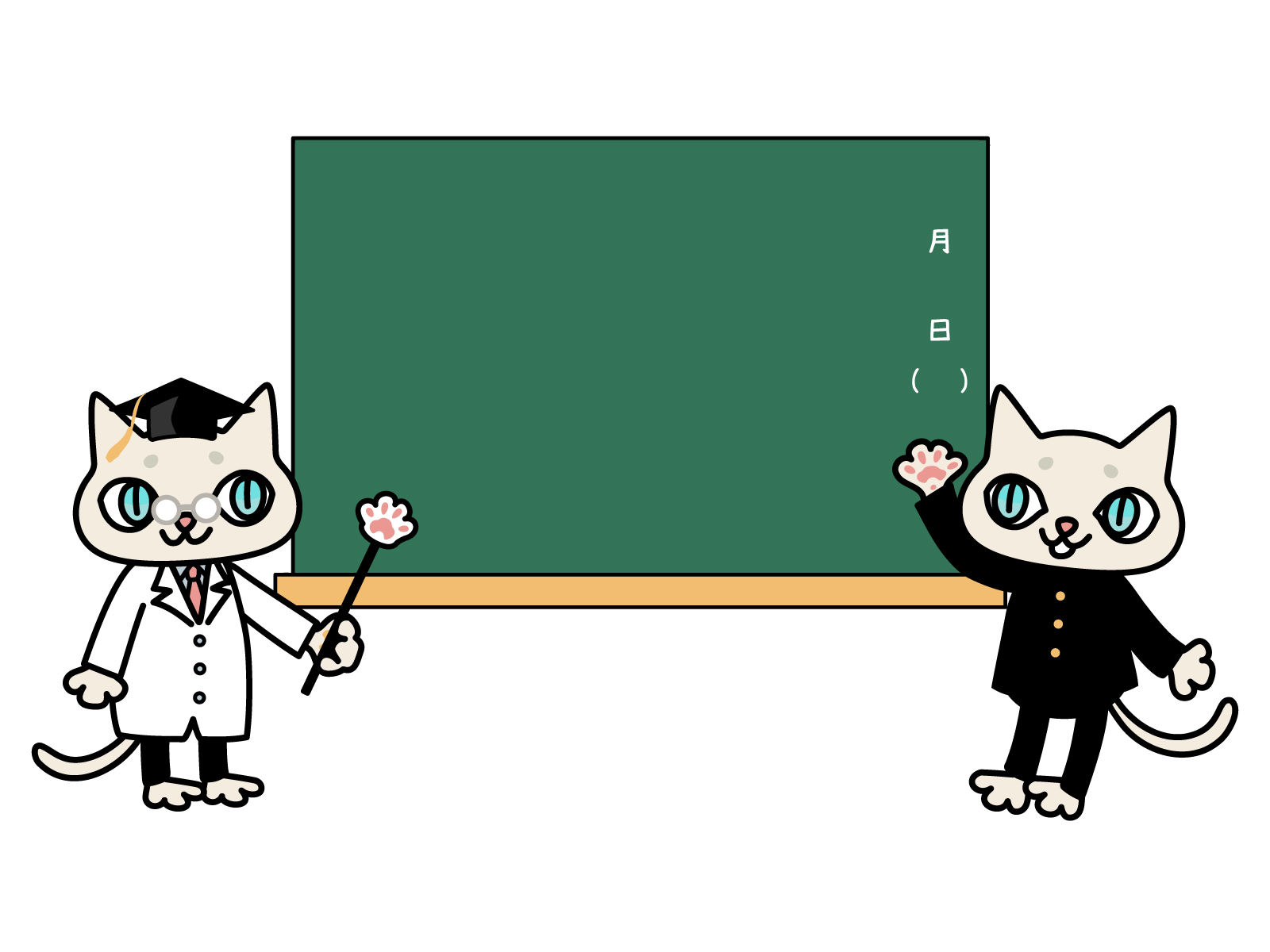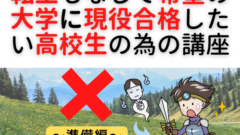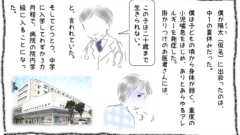塾長のテキストの選び方
前回も書きましたが、塾長は地方出身でネットなどの手段もなく、自分の勘だけを頼りにテキストをしこたま買い続けることしかできませんでした。
それでも、現在と同じような確率で当たりのテキストを引き当てられたので”まあ良し”としました。
今回はそんな体験も含めて塾長なりのテキストの選び方をお伝えしたいと思います。
自分が大学受験した時の選び方
- 蛍雪時代はもちろん、大学受験のテキストの選び方の本を購入する
- 進研ゼミの各大学合格者の体験を数十件集める
- 実力のある先生数人に質問して指示をもらった情報から絞って注文する
(田舎の本屋にあるのは漫画や雑誌、小説が中心の為)
大体10万円使ってダンボール3箱分の中でさらに厳選したテキストをヘビーローテーションで学習しました。
田舎ですから、もちろんまともな予備校などはありません。
購入したテキストの山を見た母親に「一体どれだけ買うの?」と非難されましたが、
「夏期・冬期講習も行かず勉強するにはこれくらい必要だ。」と答えたら何も言わなくなりました。
うちの田舎から大手予備校の指導を受けるには長期休暇の夏期にホテルから通わなければなりません。
そうすると、交通費・宿泊費・講習費などで30~50万円かかります。
だから、季節講習に行っている同級生は10人いなかったかもしれません。
誰が講習に参加したかなど、情報交換していたので、大体把握していましたが、360人で1割いなかったと思います。
彼らのほとんどが私立志望で、ほぼ全員東京の私立大学に進学しました。
そういうかなり不利な状況で大学受験したので、大阪に住めて予備校なども豊富に選択できる人は大変有利だと思います。
はっきり言って地方在住の生徒より、情報集めや学力向上のチャンスに恵まれています。
これだけネットが普及して、学習に関するサポートが巷に溢れているのに利用しない手はないです。
なので、積極的に情報集めをしたり、書店などに足を運んだりしない人を見ると、本当に心の底から不思議でなりません。
大学入試は、ただ親に言われるまま、学校の先生に勧められるままに受験しただけで合格できるほど甘くないので、できるだけ費用をかけたくないなら、なおさら自分の「頭」と「手足」を最大限に使うしかありません。
家庭教師・予備校講師・高校講師・プロ家庭教師になってからの選び方
天王寺だとMIOの紀伊国屋書店・アポロビルのきくや書房、近鉄のジュンク堂書店など、
そして関西一の大店舗が梅田の丸善ジュンクになります。
ここになければ、おそらくどこにもありません。
塾長は仕事の前後に梅田の丸善ジュンクによく行きました。
趣味の本を購入する為もありましたが、家庭教師の生徒のものを見るためでした。
毎月2.3回、1回1時間~5時間くらいかけて見比べ、何カ月も検討しました。
この頃は、中学入試の国語・算数・理科・社会と高校入試は全教科、
大学入試は英語・国語・小論文・AO/推薦を指導していたので、かなり時間をかけました。
テキストを実際に購入する際は平均3~4時間はいたと思います。
生徒が学校で配布されたものも参考にして考え抜いたので、市販の良い教材を見抜くのには自信があります。
定番の市販テキスト一覧
- 英語
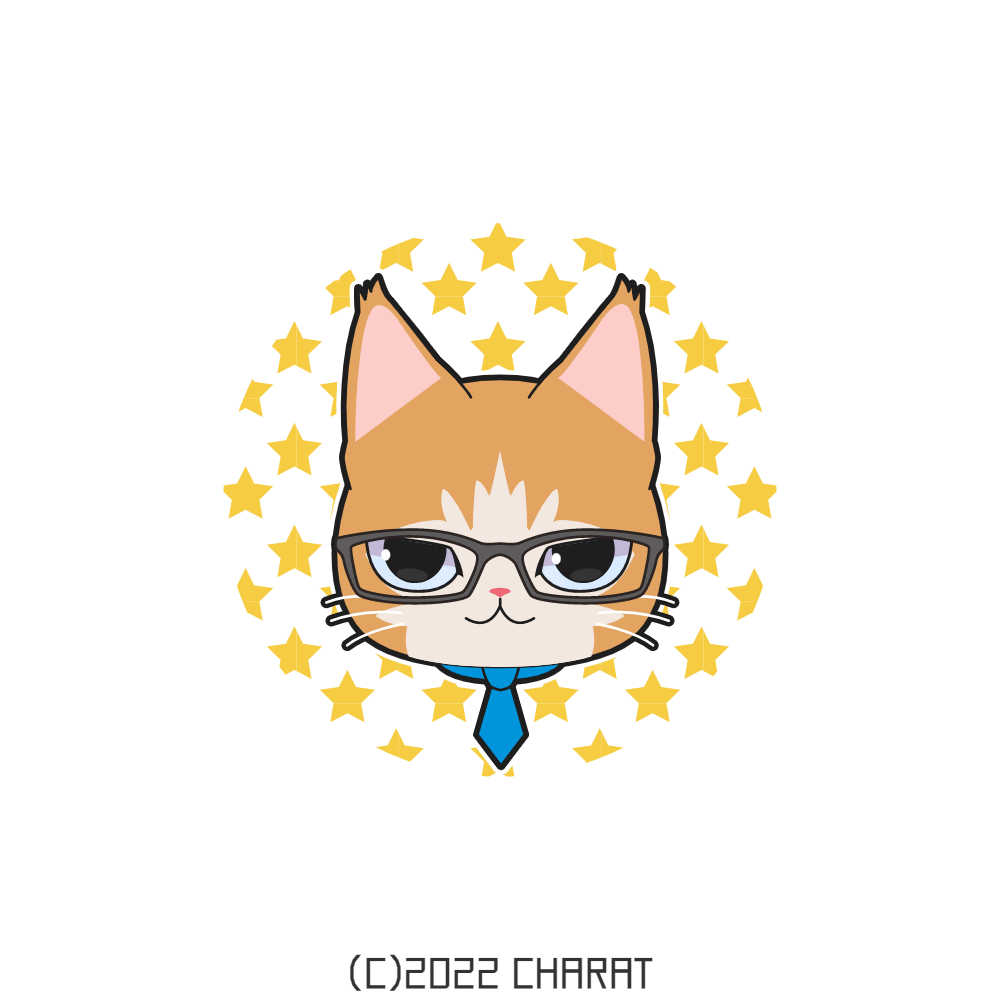
日栄社は漢文や英語で使用しました。
予備校では駿台・河合塾・代々木の物を生徒のレベルに合わせて使い分けていました。
- 数学
- 社会
- 入試対策
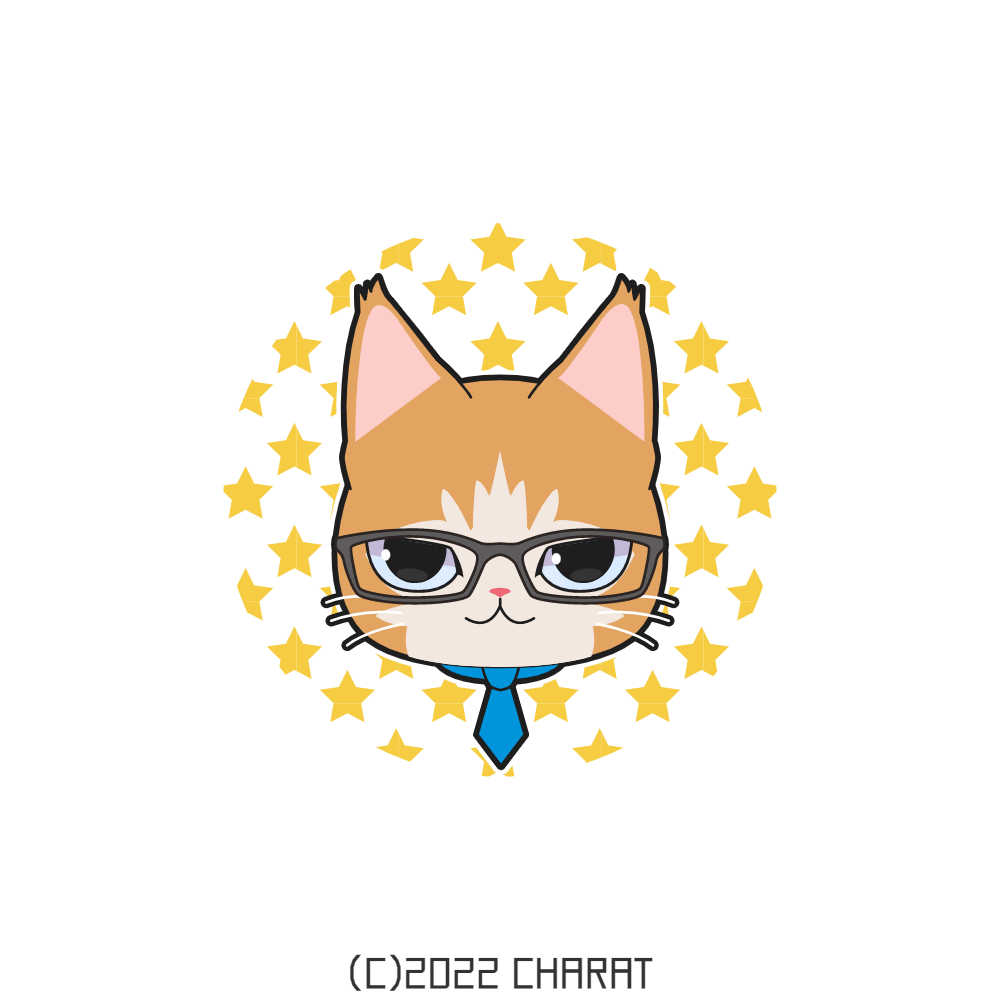
他にも色々ありますが、とりあえず今回は定番中の定番なものだけご紹介しました。
どんなにも良書でも、既に絶版になってしまったものもあります。
特に、国語のテキストは絶版本が多数あります。
今では中古で入手するしかありません。
そうやってコツコツ集めた貴重な教材たちを今でも指導に活用しています。
~番外編1~学校配布の教材だけで勝負する
学校配布のもの(教科書・辞書・参考書・問題集・漢字・英単語など)だけで勝負するという手もあります。
私立は面倒見がいいので、学校によりますが学校配布のものだけでひょっとしたら足りるかもしれません。
高校は本当に千差万別です。
授業が早い学校もあれば、ゆっくりの学校もあります。
大学進学一本槍の学校もあれば、専門学校進学や就職が中心の学校もあります。
難易度や私立・公立、エスカレーター校などで方針も様々です。
一般的には国公立大学・難関私立大学志向の高校やコースは教科書以外の参考書・問題集の配布が手厚いです。
ほぼ配られない学校(ゆるい公立・ゆったりお嬢さん学校)もあれば、
大学入試にかなり対応した豊富な量を配布する学校・コースもあります。
おしなべて私学は手厚く、公立は生徒任せの傾向にあります。
“公立の学校の場合、大量の参考書・問題集を配布するとどうしても高額になってしまい、クレームがでるからではないか?”などと、つい邪推してしまいます。
とにかく私学に比べ、生徒の自主性に任せている面があります。
ちなみに、塾長がプロ家庭教師をしていた時の話ですが、
ある中高一貫の中堅レベルの私立高校では、
上位コースはテキスト代が約5万円で、標準コースは約3万円となっており、
「内容にずいぶん差があるなあ。」と思ったことがあります。
上位コースでは、上の章で挙げたような大学入試に必要な定番の基本参考書・基本問題集がほぼ網羅されていました。
後は、学校専用の大学入試過去問からできた問題集の数々でした。
これらは指導する上でも活用しやすく助かりました。
ですので、「人に聞く」でも述べましたが、学校・予備校・塾で信頼できる・実力があると思った教師・講師に相談するのもいいと思います。
指導担当の教師ならば、弱点・強みを理解していて適切なアドバイスをもらえる可能性が高いです。
~番外編2~小中学生のうちは子どもにテキストを選ばせない方がいい理由
仕事柄、大型書店で親子が受験教材を選ぶ光景をよく見掛けます。
先日見かけたお母さんとお子さんの場合は、会話の内容からどうやら最難関校の中学受験が目的のようでしたが、高校受験の赤本コーナーでしばらく熱心に探し続けていました。
途中ようやく中学受験のコーナーへ移動したところでお父さんらしき男性が加わりましたが、結局購入には至らず、お父さんが「とにかく頑張ればいいんだ!」という発言をした後で、書店を後にしていかれました。
毎回こんな感じではないですが、「ああでもない。こうでもない。」と、迷いながら結局何も買うことなく去って行かれることが多いです。
たまに、親が子どもに選ばせて、”いいもの買ったな~”と満足気に抱えながら帰っていく場面もよく見ます。

『いや!それクソだから、絶対買っちゃダメなヤツ~~!!』
と心の中でいつも絶叫しています。
“声かけてやれよ”と思ったそこのアナタ。
絶対200%の確率で不審人物扱いされるから!!
なので、いつも静かに見送っています…。
あと、非常に稀なケースだと思いますけど、
塾の先生か家庭教師らしき人物と生徒が一緒に選んでいるのを見たことがあります。
(同業者って、言動とかで何かそれとなく気づいてしまう。)
その初老の先生はおとなしそうな生徒に、「どれがいい?」とか「どれや?」とずっと質問していました。
研究熱心な講師であれば、普段から教材研究や新刊チェック、予習をしています。
どれほど学歴が高かろうが、研究を怠ると時代からずれていき判断が鈍ると思います。
なので、最初からいきなり生徒に意見を聞くのではなく、講師が何冊かに候補を絞ってから生徒にきちんと説明するのがベストな方法です。
お子さんが現時点において解けない・分からないからこそ、テキストを購入するわけですが、
小学生や中学生くらいだと、冷静に自分の実力を分析し得意・不得意を把握することを求めるのは酷です。
大半の生徒は苦手教科の「どこが分からないのかわからない」か「最初から全部ほぼわからない」からです。
自分の長所・短所を把握しているなら、言われなくても自力で買いに来られますし、自分で克服するケースが多いと感じます。
そして、自分の苦手分野を把握できていない生徒が選ぶものは、
「全編カラー」だったり「絵がついていてわかりやすい基本的なもの」がほとんどでした。
でも、このレベルでは学校の定期テストに対応できる基礎レベル(学校の授業)程度で、入試にはほぼ役に立ちません。
なので、小中学生のうちはテキストを生徒自身に選ばせるという方法はお勧めできません。
~最後に~知名度とテキストの質は必ずしも比例しない
家庭教師時代、
「先生、いいの見つけました。」
とか
「こっちの方がいいので(or 分かりやすいので)。」
などと、指導用に指示した以外のテキストをお母さんが購入されることがよくありました。
なかには、私立文系志望で高2から記述の訓練も数学も一切学習していない我が子の意見を無視して、
「大阪大学」や「一橋大学」、場合によっては「京都大学」の過去問集を買って置いてあるお母さんもいらっしゃいました。
昔からの諺で「大は小を兼ねる」というものがありますが、
入試では「難関のテキストは標準・基礎の役に立たない」というか「全く歯が立たない」ので買っても意味がないというのが現状です。
また、テキストを選ぶ基準として、前回「よく売れているもの」「版を重ねている定番のもの」と申し上げましたが、“知名度が高いからといって必ずしも生徒自身にとって良いものであるとは限らない”のも、真実です。
ここで具体的な名称は上げられませんが、
一般的にかなり広く名が知られているテキストであっても、プロ講師からの評判が悪いものが結構あります。
レベルが低すぎて中身カッスカス、もしくはクドクドとこねくり回したような言い回しで何をさせたいのかよくわからないテキストなど、私立の学校が採用しているものでさえ、テキストとしていかがなものかと思われるものも存在します。
テキスト選びに失敗する人は、この罠に引っかかりがちなので気をつけましょう。
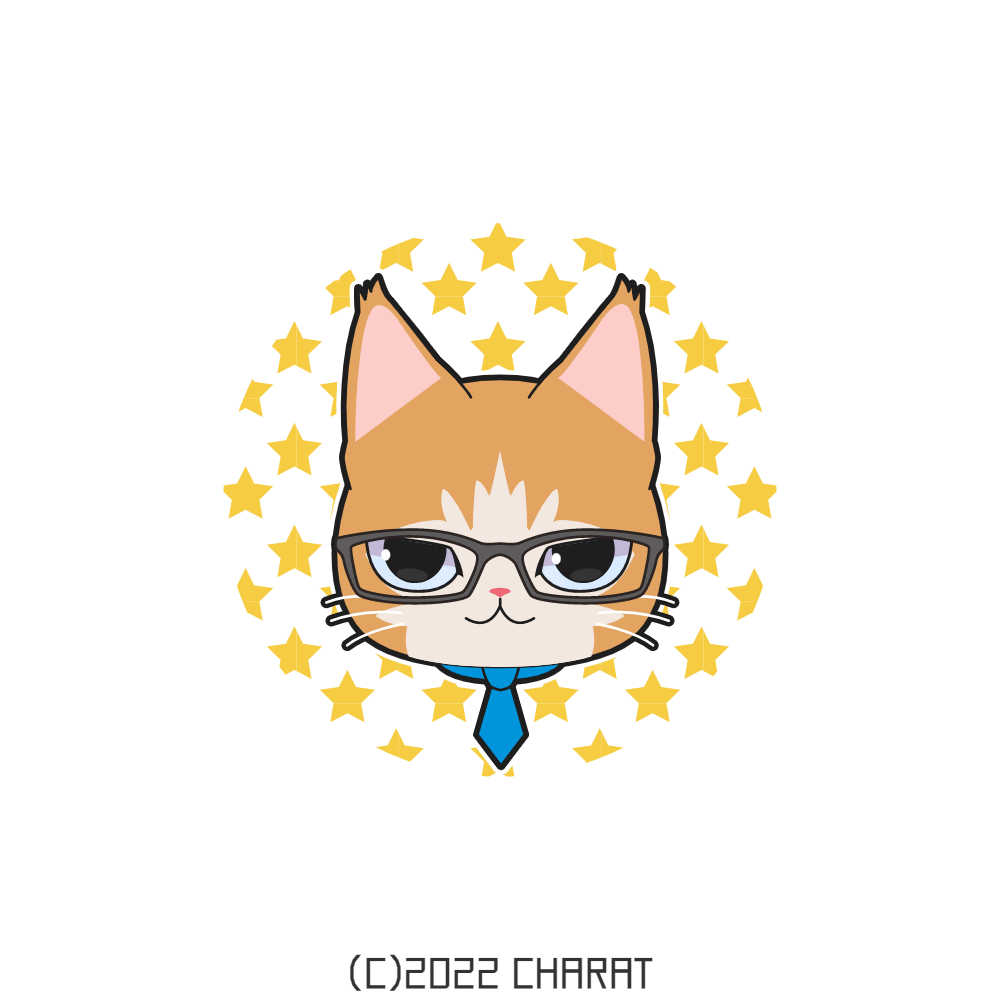
長くなりましたが、「参考書・問題集の選び方」編はこれにて終了です。
良い参考書・問題集を集めたら、次に必要なのは“学習計画を立てること”です。
次回の大学入試講座は「学習計画編」に入ります。