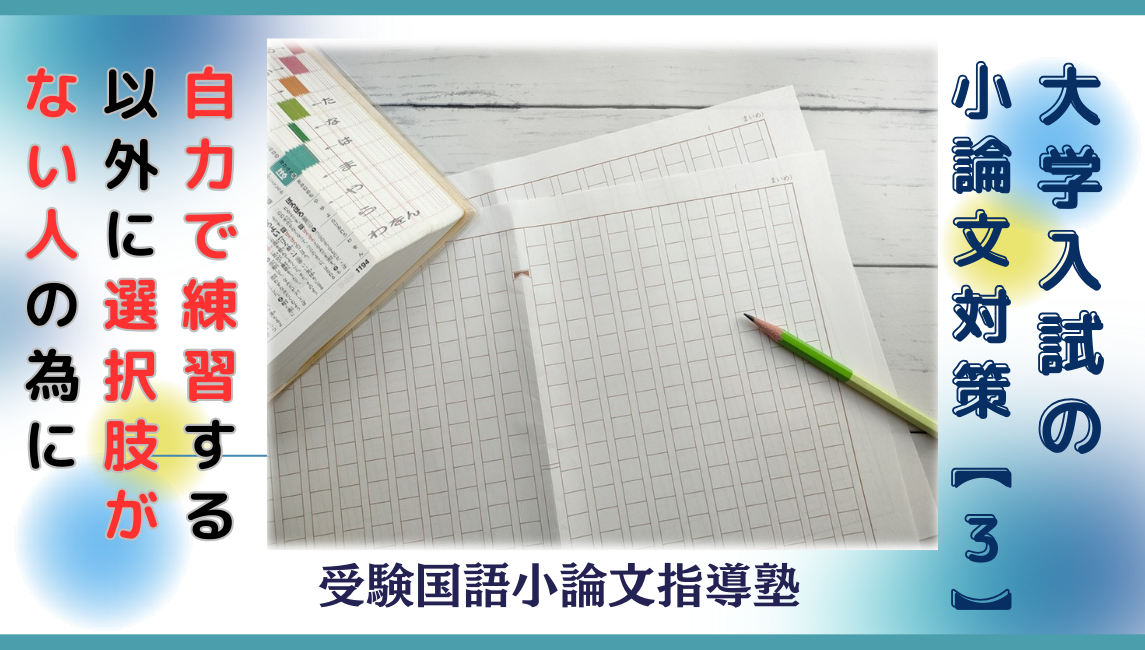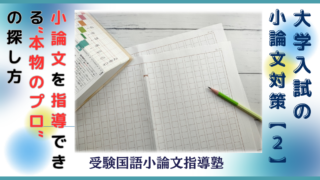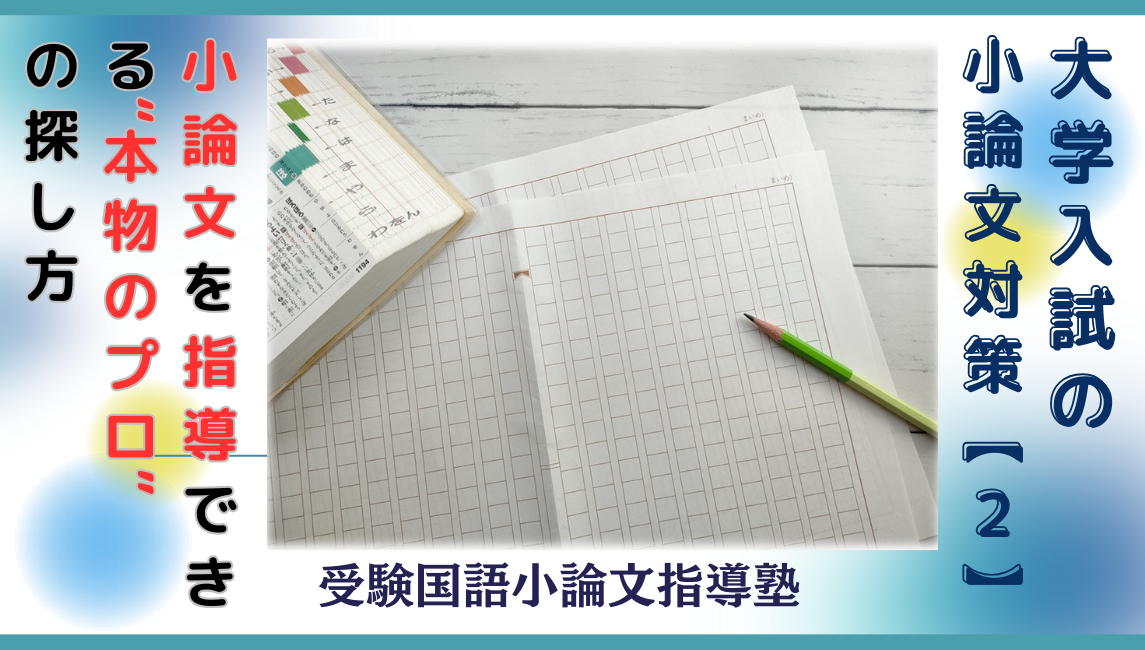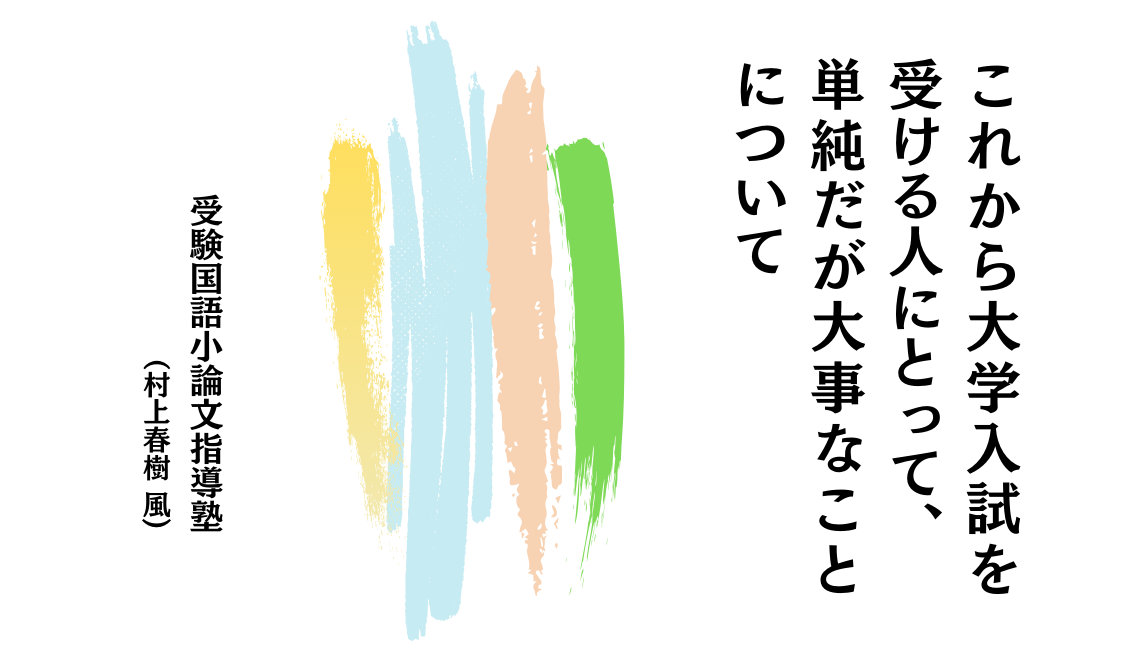前回の【大学入試の小論文対策2】小論文を指導できる本物のプロの探し方の続きです。
どうしても自力で小論文を練習するしかない人がやれるギリギリの方法

小論文を書きだす前に準備すべきこと
まず初歩中の初歩レベルな人の場合、専門の数冊に絞る前に一般教養すらない状態だと思います。
最低限の一般教養を身に着ける為には、ある程度内容がまとまった本やネットなどのメディアでお勧めされているものを基礎作りの為に買いましょう。
たとえば、有名な池上彰さんのシリーズが基礎中の基礎です。
個人の必要とするレベルに合わせて最低でも5~15冊程度読むといいでしょう。
★知識編
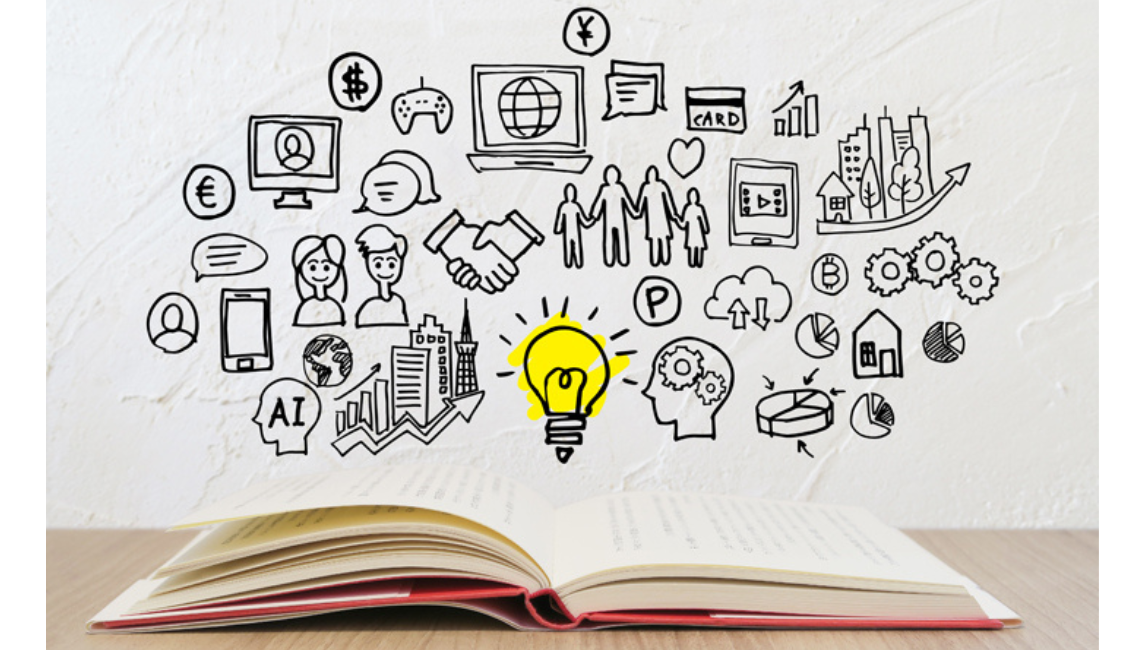
- 小論文の書き方の基礎を最低2冊買う
…2冊両方読むことにより、自分の向き不向きが立体的になって不足を補い、書ける内容もより幅広くなるので、基礎はお金を惜しまず買いましょう。
- 応用の問題集(過去問含む)を1冊以上買う
- 大学入試で自分の受ける分野(医学・人文・社会・理系など)の知識系の本を最低1冊買う
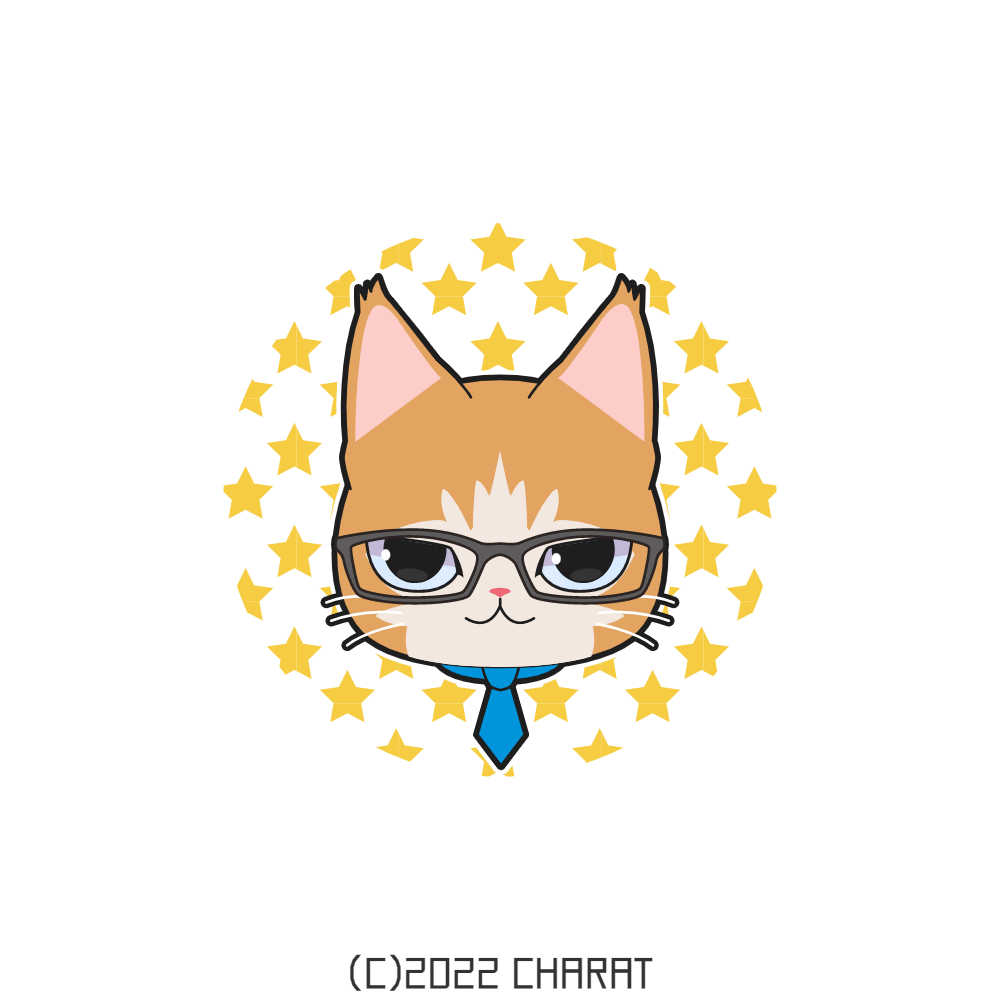
全体で最低4冊は購入されることをお勧めします。
自分の人生が掛かっているので、トータル数万円程度をここで惜しむのはやめましょう。
なぜここまで必要かと言うと、高レベルの小論文を書く記述力を身に着けるには年100冊程度の読書習慣が必要ですが、現実問題として大半の生徒がそれだけの量の本を読むわけないので、ともかく受験の為に多少チートでも必要な知識を入れるにはまとまっているものを買うしかありません。
ちなみに年100冊って言いましたけど、ライトノベルとかではなく、文学・経済学・科学・心理学・法学など、自分が興味のない分野も含めて幅広く読むのが大事ですよ!
★演習編
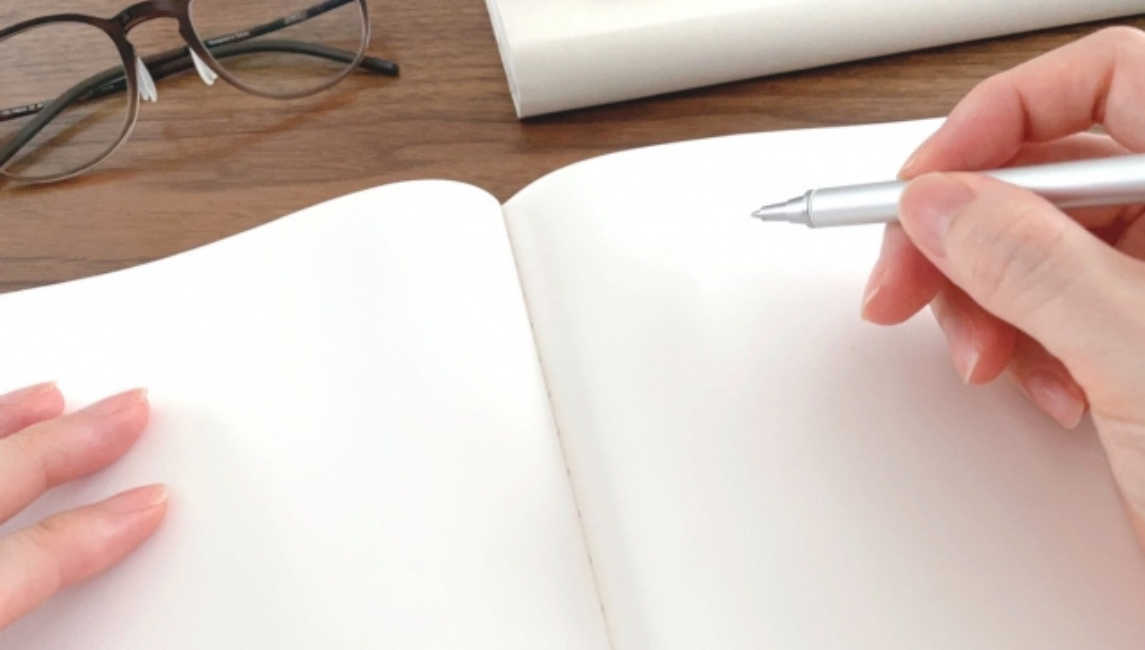
初級
【1】知識を入れつつ、初級の問題を解いていきましょう。
【2】初級レベルの添削なら、テキストを持参して学校の先生などに簡単な感想をもらう程度に見てもらってください。
どうしても見てくれる先生が身近にいない場合、先輩か友達でもいいから印象だけでも教えてもらってください。
中級
初級レベルの文章を書けるようになった手応えを感じ、知識もある程度ついてきたら、中級(応用編)に入ります。
【1】この段階で時間内に書けることはほぼないので、まず時間制限なしで書きましょう。
【2】すぐに添削せずに自分で知識を調べて、1よりは具体的なものを書く挑戦をしましょう。
【3】模範解答を見て、論の展開とどんな知識かを見ましょう。
【4】文章の筋道、骨子がきちんとルールに則っているかを確認しましょう。
【5】是非を問う問題なら、本来なら最低でも5パターンは考えられるはずですが、とりあえず最低3パターンは書いてみましょう。どうしても無理なら2パターン書きましょう。
まったく異なるパターンの小論文が書けるようになると、多角的に物事を見たり考えたりできるようになるはずです。この視点・考え方ができるようになると、小論文が全然書けなくて困るということはなくなるはずです。
自分一人でも演習を繰り返すことで少なくとも知識はついていき、様々な模範解答を読むことである程度書けるようになっていくはずです。
小論文を指導していると、かなり学力が高い生徒でも誤字脱字や漢字が書けない人が多いので、致命的なミスをおかさないよう言わずもがなでやっておきましょう。
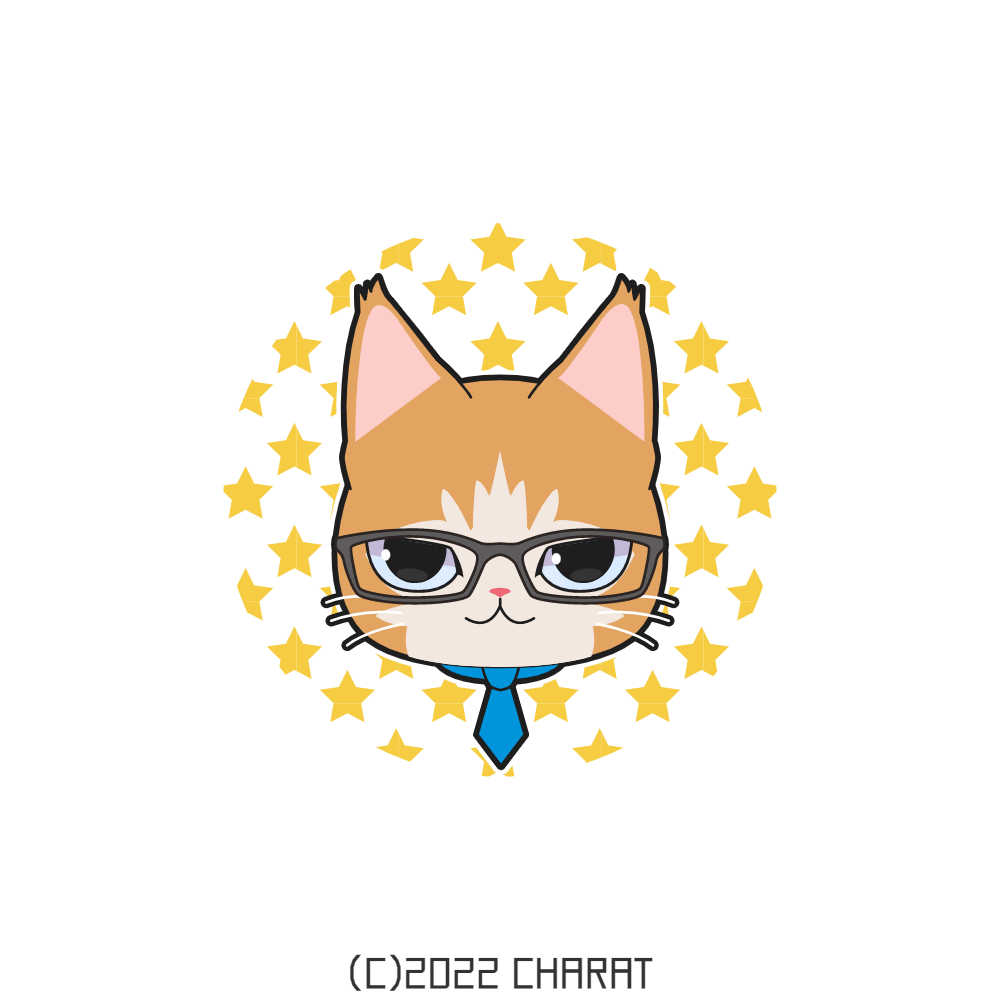
国語知識(漢字・語彙・慣用句・ことわざ)がない人は大学入試の問題集をプラス1冊こなしましょう。
小論文の基礎的な形式や誤字脱字は論外ですよ。
上級
時間内かつ制限字数で演習問題がこなせるようになったら、過去問題にチャレンジしましょう。
“先生”と呼ばれる職業の人でも、知識不足と指導力がないために何の訓練もさせずにいきなり過去問を解かせようとする人がたまにいます。
しかし、書く力と知識もない段階で、急に入試問題を解いても実力がつくわけがありません。
これは、自動車教習所できちんとした指導を受ける前に、いきなり路上運転させられたあげく、教わってもいないことをずっと注意を受け続けるのと変わりません。
【1】時間を計って、時間内で書き上げるようにしましょう。
【2】今度は知識を調べて、時間を計らずに書いてみましょう。
【3】まず自分で模範解答を確認します。それから、自分の書いた原稿と模範解答を学校の先生か友達に見せて、大体の感想や印象を聞いてみましょう。
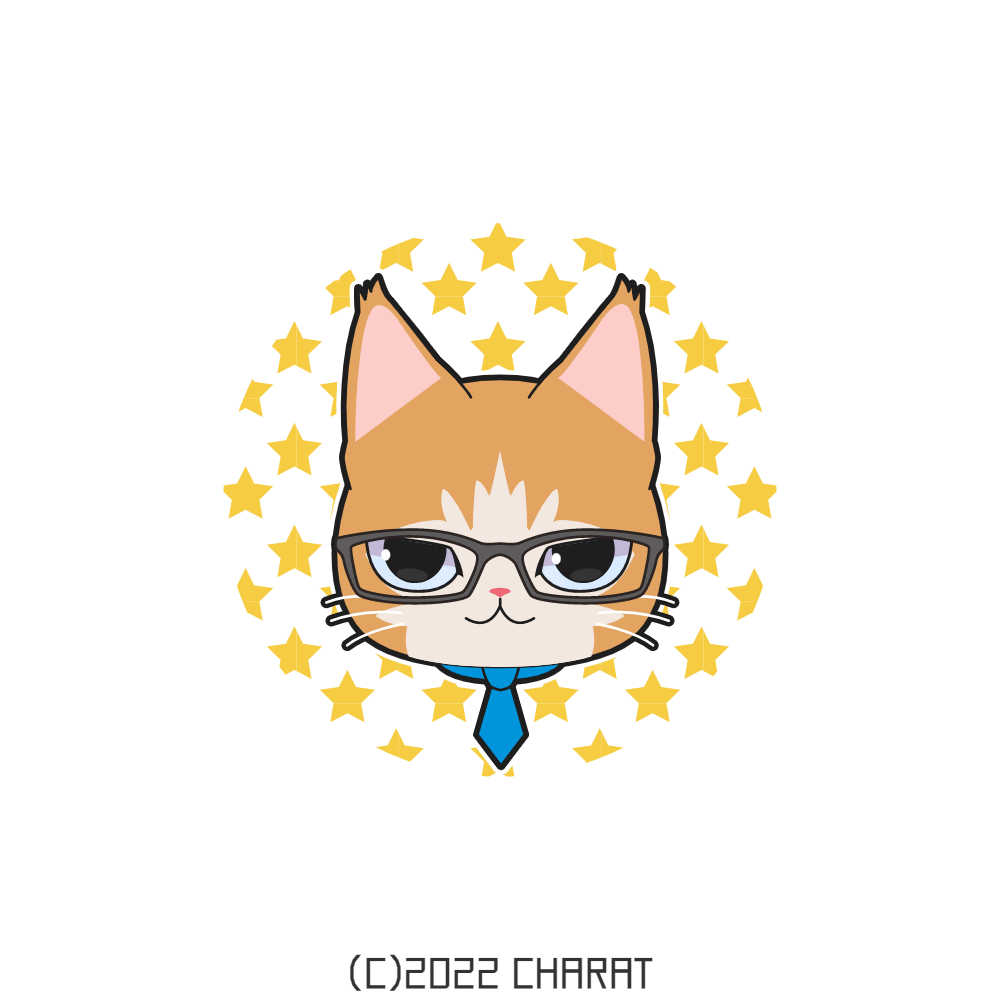
プロの訓練なしで自力でできるのはここまでです。
あともう一つ付け加えることがあるとすれば、小論文と面接をちゃんとセットで練習できているか?ぐらいですね。
塾長は、学生時代に小論文の基礎の本を1冊読んで全国模試で7位を取ったったことがあります。
田舎でろくな塾や予備校もない中、小論文を書き上げる力がついた理由は、約1万冊くらいの本をジャンルを問わず幅広く読んでいたお陰だと思います。
例えば、科学雑誌ニュートン、当時の最先端だったセラミックの本、法学の本、文学はもちろん心理学など、自分が好きでない分野も高校に入ってから努力して幅広くたくさん読むようにしていました。
ジャンルの違う大量の本を読むことで知識が繋がっていきます。
いわゆる、莫大な”暗黙知”が形成されていったのだと思います。

ですので、一つの質問について解答や筋道がいくつも浮かんで、それを理論的に書くことが日常的にできるようになったのだと思います。
もし余力がある人は、様々な分野の本を大量に読めば小論文を書く為の材料に困ることはありませんので、挑戦してみてください。